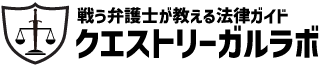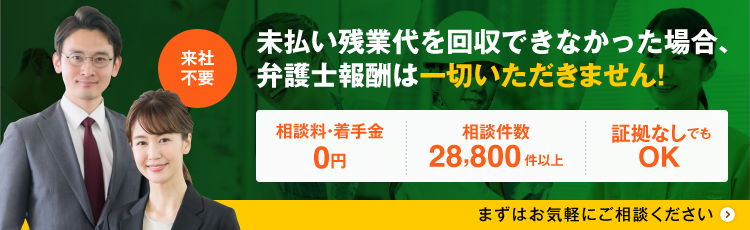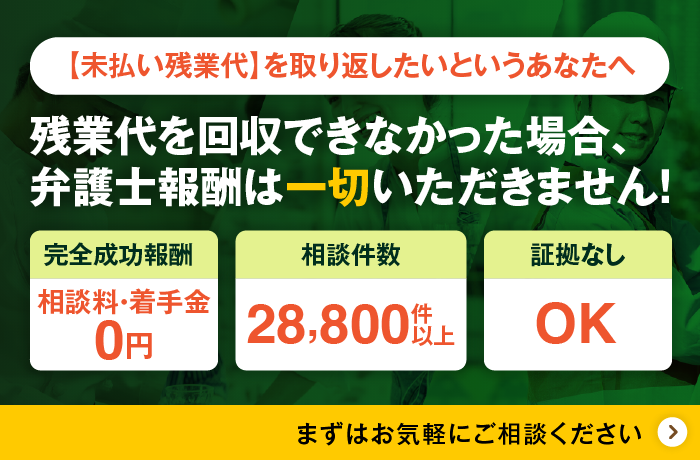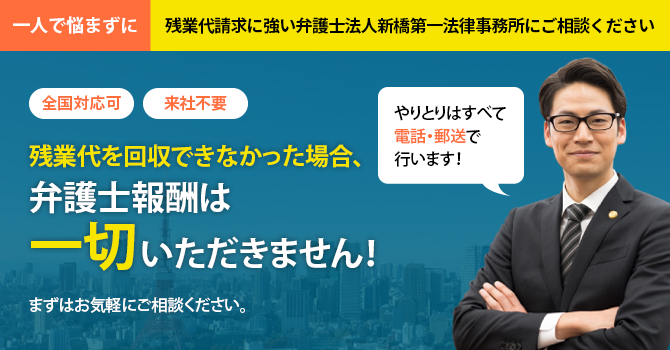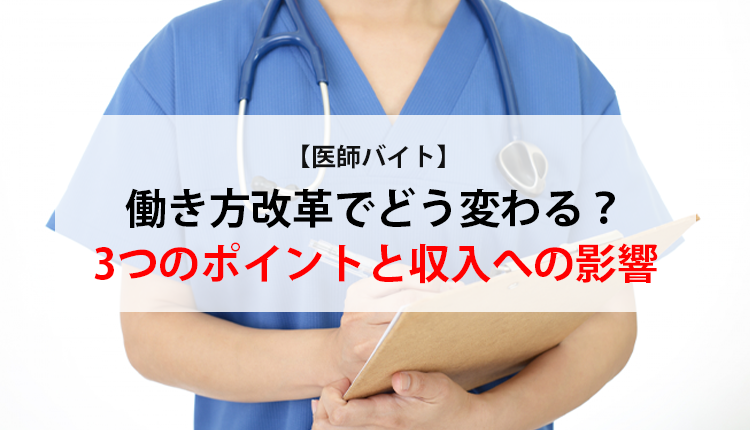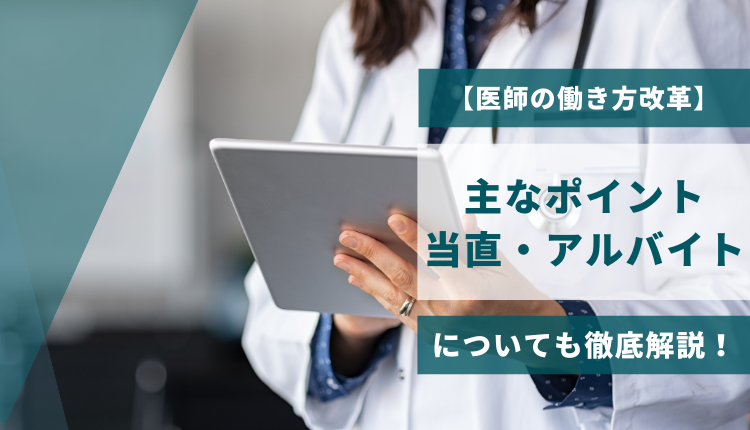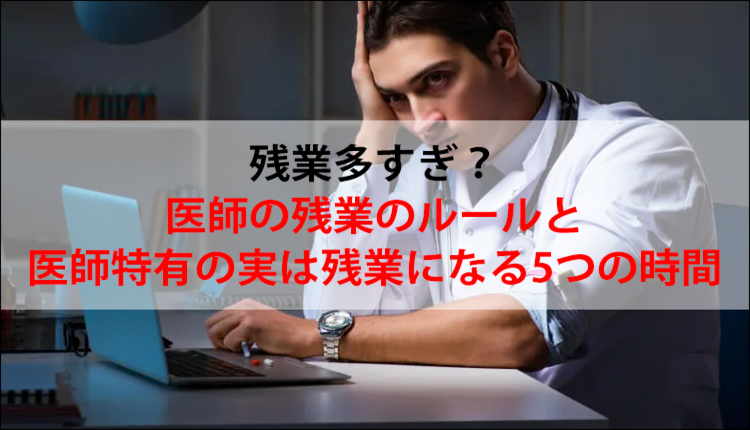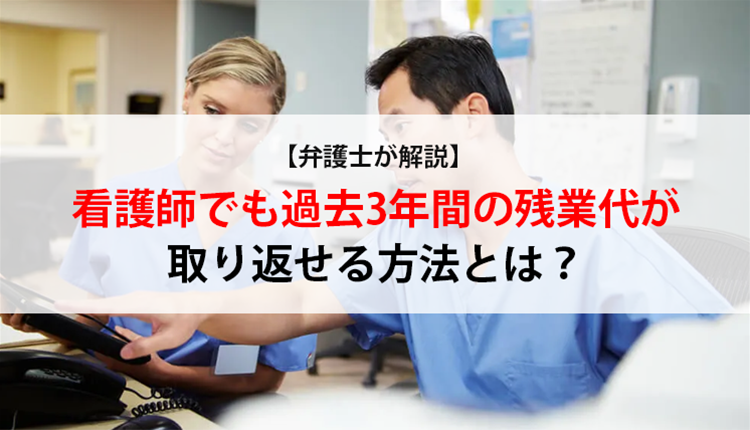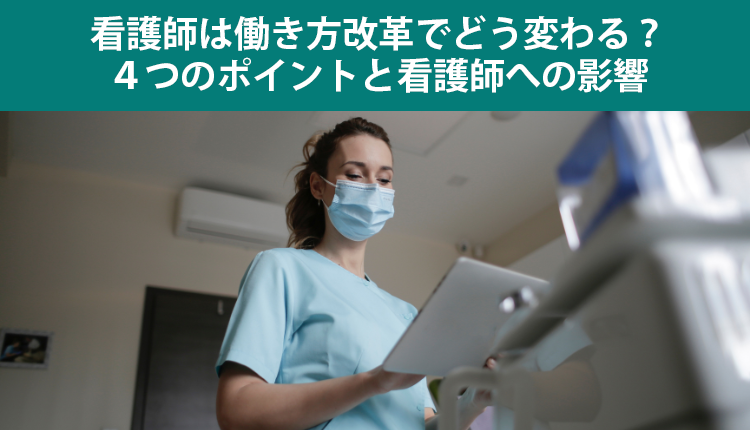【看護師と2024年問題】働き方改革の影響と今後の課題
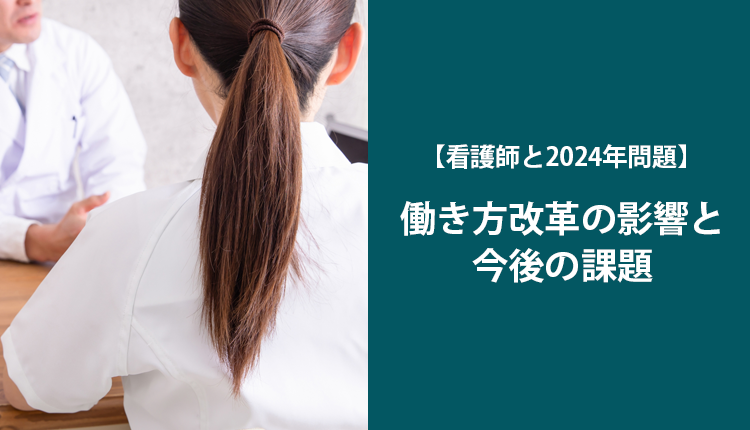
この記事を読んで理解できること
- 医療の2024年問題による看護師への影響
- 2024年問題以降も重要な看護師の働き方改革のポイント
- 看護師の働き方の実態と今後の課題
あなたは、
- 医療の2024年問題による看護師への影響が知りたい
- 夜勤や時間外の労働時間はどうなる?
- 人手不足が深刻化しないか心配
などとお考えではないですか?
2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が適用されるため、医師の勤務時間の削減が、医療界にとって最も重要な課題の一つとなっています。
これが医療の2024年問題と言われ、次にあげる3つの問題だけでなく看護師に与える影響も大きいと考えられます。
- 医師からのタスクシフト・シェアで仕事が増える可能性がある
- 負担を減らすため他職種へのタスクシフトも必要になる
- 看護師を含め医療スタッフの勤務環境の整備がより求められる
そのため、看護師の働き方改革だけでなく、看護師に求められる業務内容の変化についても十分理解することが重要です。
そこでこの記事では、
1章では、医療の2024年問題による看護師への影響を
2章では、2024年問題以降も重要な看護師の働き方改革のポイントを
3章では、看護師の働き方の実態と今後の課題
について解説します。
この記事を読んで、医療の2024年問題と看護師の働き方改革のポイントをしっかり理解し、今後の活動に役立てて下さい。
1章:医療の2024年問題による看護師への影響
ここでは、医療の2024年問題による看護師への影響について4つ紹介します。
仕事をするにあたって、医師の働き方改革は看護師にも大きな影響があります。
そのため、しっかりと確認しましょう。
- 医師からのタスクシフト・シェアで仕事が増える
- 負担を減らすため他職種へのタスクシフトも必要になる
- 人手不足がより進行する
- 勤務環境の整備がより求められる
それぞれ順番に解説します。
1-1:医師からのタスクシフト・シェアで仕事が増える
医療においてのタスクシフト・シェアとは、医師のさまざまな業務を見直し、医療の安全性向上・効率化を目的として、業務の一部を看護師に移管したり、共同実施することです。
タスクシフト・シェアは、医療従事者がそれぞれの専門性を活かせるように、業務の分担をし、チーム医療の水準をあげるメリットがあります。
一方で、タスクシフト・シェアにより、医師の業務が移管されるため、看護師の業務が増え、長時間労働や時間外労働に繋がることが問題視されています。
そのため、看護師の負担を少なくし、長時間労働や時間外労働をしなくてもよいような対策が必要になります。
1-2:負担を減らすため他職種へのタスクシフトも必要になる
2024年4月から適用される「医師の働き方改革」で、医師の労働時間の削減が求められるためタスクシフト・シェアが増えます。
そのため、看護師の負担が大きくなるので、負担を減らすため他職種へのタスクシフトも必要になります。
看護師のタスクシフトの一環として、服薬指導や残薬確認を薬剤師に、口腔ケアを歯科衛生士に移管するなどの動きが挙げられます。
他職種へのタスクシフトを増やすことで、看護師の負担を減らし持続可能な働き方を作ることが大切です。
1-3:人手不足がより深刻化する
2024年4月に制定される「医師の働き方改革」により、看護師の人手不足がより深刻化することが予想されます。
現状でも、少子高齢化による労働力の減少や、過剰な業務量の多さなどで、看護師になる人の割合は年々低くなっています。
また、看護師の多くは女性なので、結婚や出産といったライフステージとの両立が難しく離職する人の割合が高いです。
更に、医師の働き方改革が実施されることで、看護師の業務が従来より増加するため、ワークライフバランスが崩れる可能性が高まります。
そのため、看護師になる人材が減り、人手不足がより深刻化するおそれがあります。
1-4:勤務環境の整備がより求められる
少子高齢化による人口の減少や、医療ニーズの増加、医療機関の偏在などがあり、看護師の就職率が下がり、離職率が高くなっています。
そのため、医療機関の勤務環境の設備がより求められます。
また、医師の働き方改革により、看護師の業務が増加するに連れて、健康で安全に働くことが出来るように、より質の良い勤務環境の整備が大切です。
2章:2024年問題以降も重要な看護師の働き方改革のポイント
2024年問題以降も、重要な看護師の働き方改革のポイントは多くあります。
今後のポイントを抑え、働きやすい環境作りを目指しましょう。
- 夜勤負担を減らす
- 時間外労働を減らす
- 暴力・ハラスメントをなくす
- 仕事のコントロール感を持てるようにする
- 仕事・役割・責任に見合った評価と賃金を求める
それぞれ順番に解説します。
2-1:夜勤負担を減らす
2024年問題で、看護師の業務が激化することが予想されるため、夜勤の負担を減らすことは重要です。
最近では、看護師の夜勤時間は、16:00〜9:00が一般化しつつあります。
また、月平均夜勤時間72時間要件で、病院全体で見た際に、平均して看護師一人あたり夜勤の時間は72時間と定められています。
しかし、夜勤は生活リズムが崩れることで、無意識の内に疲れをためこんでしまうケースがよくあります。
そのため、夜勤の人数を増やす、少しでも睡眠時間を確保するなど、夜勤負担を減らす対策が必要になります。
2-2:時間外労働を減らす
2024年問題以降も看護師が働く際に重要なポイントは、時間外労働を減らすことです。
看護師の時間外労働が多い原因としては、勤務形態や、突発的な患者への対応、時間外の研修や勉強会が挙げられます。
しかし働き方改革によって、看護師の時間外労働の上限が、特別な事情がある場合でも年間で720時間以内と定められているため、違反した場合は病院に罰則が科される可能性があります。
罰則としては労働基準法119条により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。
そのため、時間外労働を減らす対策として、新たな勤務形態の導入や業務内容の改善、突発的な状況をカバーできる環境作りが必要です。
2-3:暴力・ハラスメントを無くす
看護師における、暴力・ハラスメントは、上司や同僚の他に患者様から受けるものが多いです。
そのため、対策として、医療従事者が患者やその親族からの暴力・ハラスメントに対して学習できる教材を作成しています。
また、2024年問題にあたって、看護師の持続可能な働き方を目指す場合には、更に暴力・ハラスメントを無くす対策が必要です。
2-4:仕事のコントロール感を持てるようにする
仕事のコントロール感とは、職場の中で個人の能力に応じて任せられた仕事を、自分のペースで行えるように順番や方法を自ら決定し、職場の仕事方針に自分の意見を反映できることです。
看護師は、突発的に、手術や患者様の対応をしなければなりません。
また、患者様やその家族の心身をケアする、精神的な心の看護も必要です。
そのため、スケジュール管理、円滑なコミュニケーション能力、ストレス発散といった、仕事のコントロール感を持てるようにすることが大切になります。
2-5:仕事・役割・責任に見合った評価と賃金を求める
2024年問題で、看護師の業務が増加するにつれて、仕事・役割・責任に見合った評価と賃金を求める動きは大切です。
2019年には、賃金を上げる取り組みとして「日本看護協会」から4つ提案されています。
- 職務遂行能力や担っている役割、専門性による貢献に応じた評価と処遇とする
- 評価と処遇に関する制度の運用としては、公平性、納得性が担保できる評価者教育・研修を継続して行う
- 個々の看護職の多様な働き方や貢献に見合った評価と処遇とする
- 自己の課題やキャリア開発について主体的に取り組み、役割を実践していく
※参照:日本看護協会「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」
しかし、2024年からは、看護師の持続可能な働き方を目指すため、更に改善が必要になります。
3章:看護師の働き方の実態と今後の課題
看護師が働くにあたって、実態を確認し今後の課題を克服していくことは大切です。
ここでは、看護師の働き方の実態と、今後の課題を紹介します。
3-1:看護師の働き方の実態
看護師の働き方の実態として、次の2つを取り上げます。
- 看護師の現状の業務時間
- 看護師の現状の業務量
それぞれ順番に解説します。
3-1-1:看護師の現状の業務時間
看護師の現状の勤務体制と勤務時間は、以下になります。
|
勤務体制 |
出勤時間 |
休憩時間 |
退勤時間 |
|
日勤 |
8時 |
1時間 |
17時 |
|
夜勤 (2交代制) |
16時30分 |
2~3時間 |
9時 |
|
夜勤 (3交代制) |
24時 |
1時間 |
8時30分 |
|
準夜勤 |
16時 |
1時間 |
24時30分 |
一般的な勤務体制と勤務時間は上記になりますが、所属する病院、部署によっては異なります。
救急搬送が多い総合病院や、重症患者が搬送されることが多い基幹病院は勤務時間が多くなります。
残業については、日本看護協会が行った「2021年 看護職員実態調査」によると、1か月で平均17.4時間です。
しかしその中で、実際の残業時間と、申告した残業時間の差の平均が8.6時間あり、サービス残業になっています。
看護師は残業が常態化している一面があるため、サービス残業が多くなる可能性が高いです。
3-1-2:看護師の現状の業務量
看護師は、基本的な看護業務の他、患者のケアなども求められる仕事です。
看護師の基本的な業務内容としては、以下の10個があげられます。
- 問診
- 検査補助
- 点滴
- 採血
- 投薬
- バイタルチェック
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 日報記録
看護師は、一日でこれだけの業務をこなさなければなりません。
また、患者の容態が急変した際の、突発的な緊急の対応ができるように、患者の様子をチェックする必要もあります。
更に、新たな知識の勉強や資格の勉強も、看護師に必要な業務の一環です。
所属する部署によって業務の量も異なりますが、現状の看護師は、患者の生命維持や食事・排泄の補助など、多岐にわたる業務量を1日でこなさなければなりません。
3-2:今後の課題
看護師の今後の課題は、以下の2つです。
- 十分な休憩時間の確保
- 業務量の減少の徹底化
それぞれ順番に解説します。
3-2-1:十分な休憩時間の確保
看護師の今後の課題は、十分な休憩時間の確保です。
しかし、医師からのタスクシフト・シェアにより、看護師の業務が多くなることで、休憩時間の確保が難しくなる可能性があります。
その結果として、疲労によるヒューマンエラーの増加が懸念されます。
そのため、看護師・医療スタッフの増員や、勤務形態を工夫することによって、十分な休憩時間が確保できる医療体制が求められます。
3-2-2:業務量削減の徹底化
看護師の持続可能な働き方を目指すうえで、今後の課題として、業務量削減の徹底化が必要です。
先述しましたが、看護師の業務は、基本的な看護業務の他、患者のケアなども求められます。
そのうえ、タスクシフト・シェアによる医師の業務を移管する場合は、看護師の業務は更に多くなります。
そのため、他職種に任せることができる業務を割り出し、タスクシフトをするなど業務量削減の徹底化が必要です。
まとめ:医療の2024年問題による看護師への影響
最後に、今回の記事の内容をまとめます。
医療の2024年問題による看護師への影響について4つ
- 医師からのタスクシフト・シェアによって、看護師の業務量が増える
- 看護師の業務への負担を減らすため、他職種へのタスクシフトも必要になる(服薬指導や残薬確認を薬剤師に、口腔ケアを歯科衛生士に移管するなど)
- 少子高齢化による労働力の減少や、出産や結婚によるライフワークバランスの両立が難しくなり、人手不足がより深刻化する
- 不規則な勤務状態や看護ニーズの増加などによって環境整備が追いついてかない
2024年問題以降も重要な看護師の働き方改革の4つのポイント
- 2024年問題で、看護師の業務が激化することが予想されるので、夜勤の負担を減らすことが必要
- 新たな勤務形態の導入や業務内容の改善、突発的な状況をカバーできる環境作りといった、時間外労働を減らす対策が必要
- 上司や同僚の他に患者から受ける暴力・ハラスメントの対策
- 仕事・役割・責任に見合った評価と賃金を求める動き
看護師の働き方の実態
- 救急搬送が多い総合病院や、重症患者が搬送されることが多い基幹病院は残業が多くなるので、業務の時間が多い
- 現状の看護師は、患者の生命維持や食事・排泄の補助など多岐にわたる業務量がある
看護師の今後の課題
- ヒューマンエラーを引き起こさないように、十分な休憩時間の確保ができるような体制が大切
- 看護師がタスクシフトをするなど業務量削減の徹底化が必要
この記事の内容をしっかりと理解して、あなたにとってベストな働き方をしましょう。