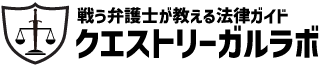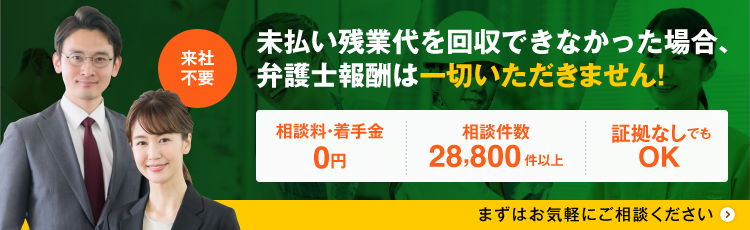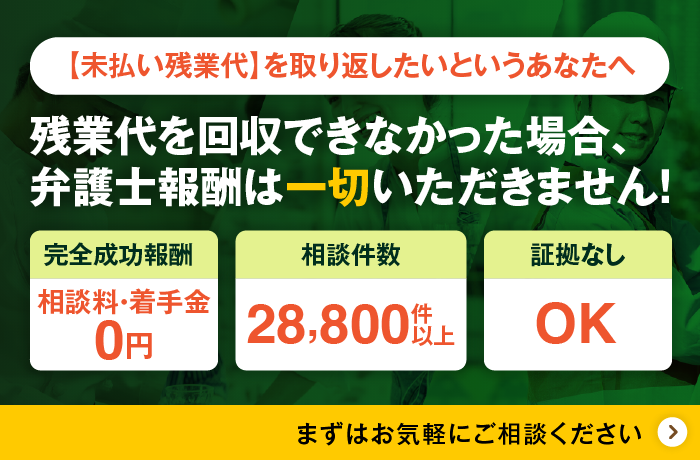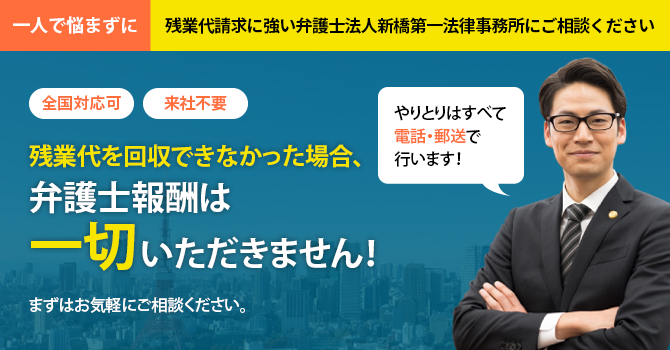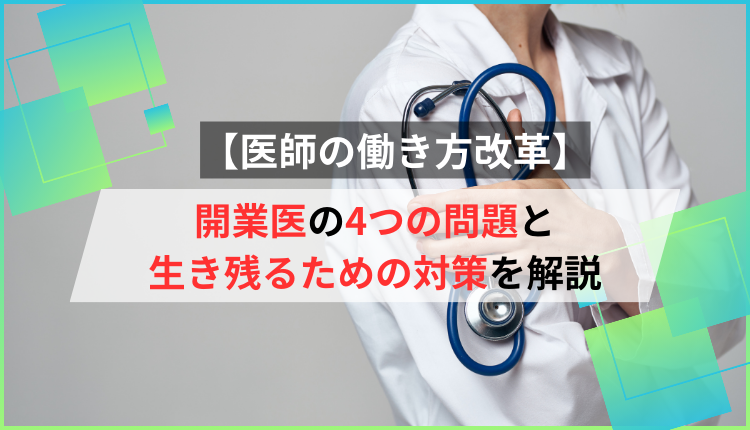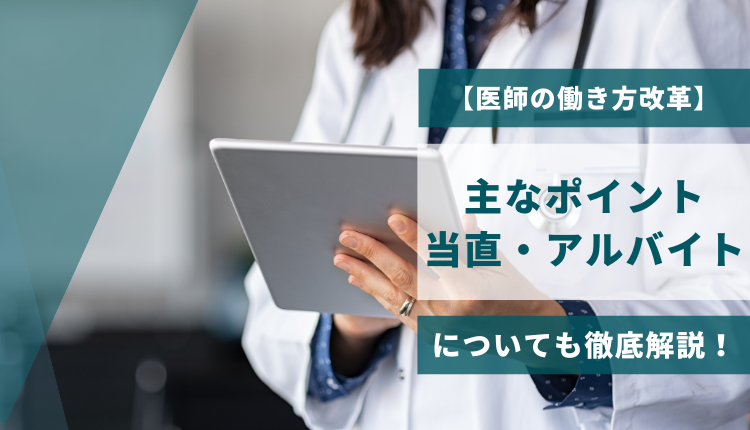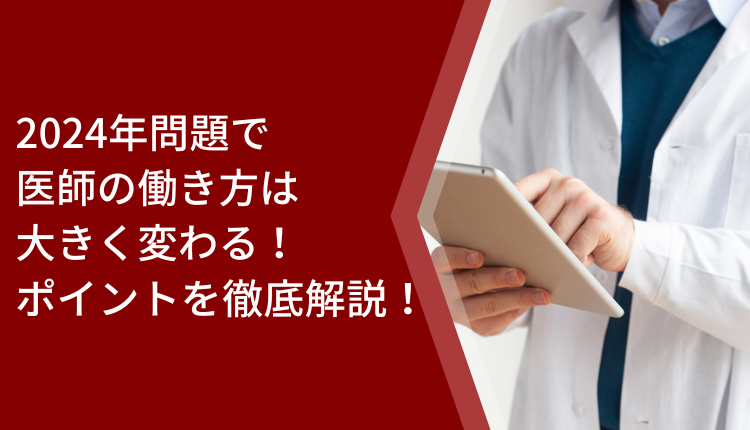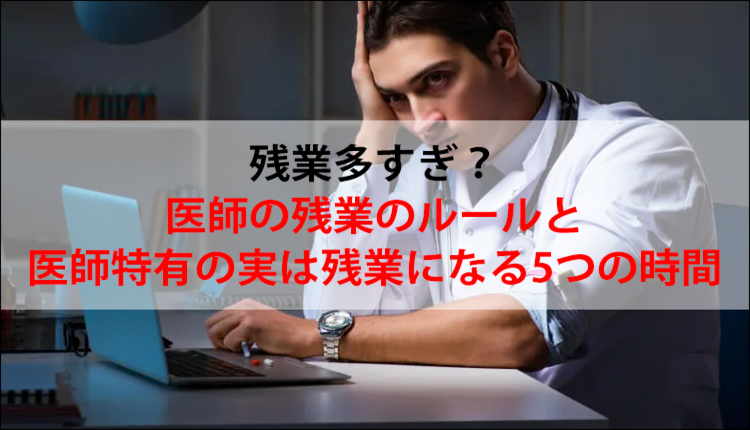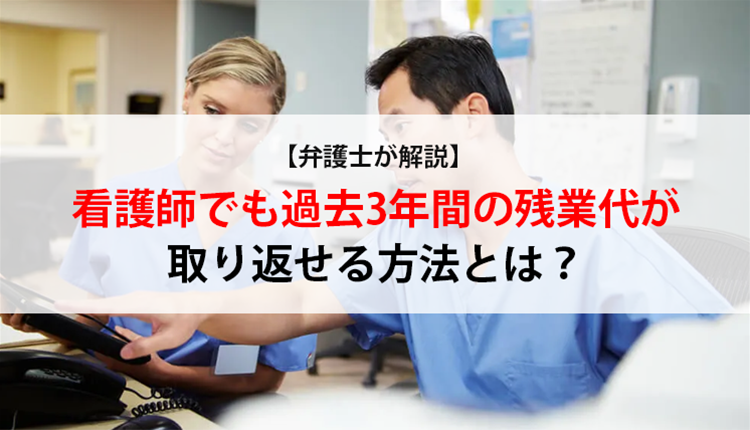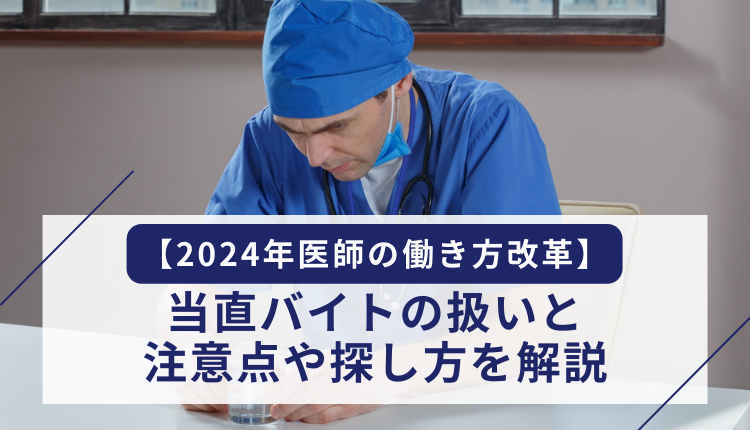【医師バイト】働き方改革でどう変わる?3つのポイントと収入への影響
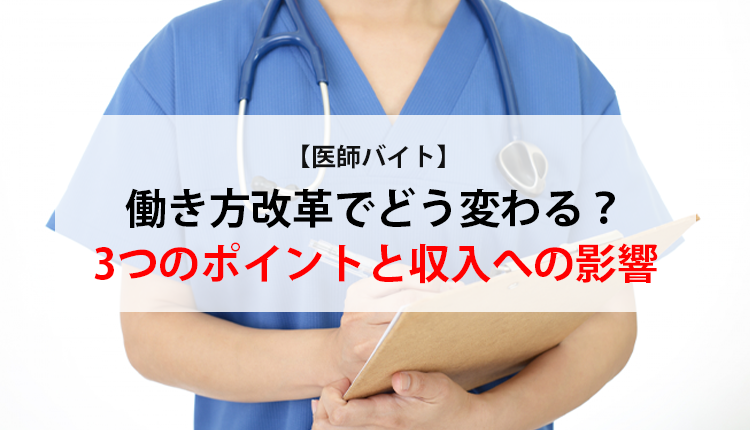
この記事を読んで理解できること
- 医師の働き方改革による医師バイトに影響
- 働き方改革による収入への影響
- 働き方改革で収入を確保するための対策
あなたは、
- 医師の働き方改革で医師バイトへの影響が知りたい
- 医師の働き方改革で非常勤・当直バイトも制限される?
- 働き方改革後も収入が確保できるか心配
などとお考えではないですか?
結論から言うと、医師の働き方改革によって、医師も時間外労働の上限規制が適用されるため、非常勤や当直などの医師バイトも制限される可能性があります。
なぜなら、本来務めている医療機関の時間外労働だけでなく、他の医療機関での医師バイトの時間外労働も合算されるからです。
そのため、働き方改革による医師バイトへの影響として、次の3つがあげられます。
- 副業・バイト先での労働時間が制限される可能性がある
- 宿日直許可があるバイト先での勤務時間はカウントされない
- 働き方改革によって労働時間の管理方法が変わる
これらのポイントをしっかり理解することが重要です。
これらの知識を知らずに働いていると、あなたにとって大きな損になってしまう可能性もあります。
そこでこの記事では、
1章では、医師の働き方改革による医師バイトへの影響
2章では、医師の働き方改革による収入への影響
3章では、働き方改革施行後も収入を確保する方法
について、詳しく解説します。
この記事を読んで、働き方改革後もしっかりと収入を維持できるように対策しましょう。
1章:医師の働き方改革による医師バイトに影響
多くの医師は、常勤先と異なる勤務先の医療機関での、アルバイトで収入を得ています。
なかでも、厚生労働省の調査によると、大学病院の常勤勤務医の9割以上がアルバイトをしているという結果が出ています。
ここでは、「時間外労働の上限規制」により、医師バイトに与える影響について紹介します。
- 医師の働き方改革の3つのポイント
- 副業・バイト先での労働時間もカウントされる
- 宿日直許可がある副業・バイト先での勤務時間はカウントされない
- 医師の労働時間の管理方法とペナルティについて
それぞれ順番に解説します。
1-1:医師の働き方改革の3つのポイント
医師の働き方改革におけるポイントとして、次の3つがあげられます。
- 勤務医の時間外労働は原則「960時間以下」
- 連続勤務時間制限と勤務間インターバル・代償休息
- 月60時間を超える時間外割増賃金率の引き上げ
それぞれ解説します。
1-1-1:勤務医の時間外労働時間は原則「年960時間以下」
働き方改革が発足されると、ワーク・ライフ・バランスを目的として、時間外労働に上限規制が適用されます。
上限規制では、医療機関がA・連携B・B・C-1・C-2水準の5つに分類され、業務の内容や、役割によって年間の時間外労働の内容が異なります。
|
水準 |
対象 |
理由 |
年間の時間外労働時間 |
|
A |
原則、日本に位置する全ての医療機関 |
場合によっては、長時間労働が必要な際の水準 |
960時間 |
|
連携B |
医師が派遣先として行く医療機関 |
地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働となるため |
1860時間 |
|
B |
地域医療確保のため、医療派遣を行っている医療機関 |
地域医療を確保するため |
1860時間 |
|
C-1 |
臨床研修医、専門研修医の医療機関 |
しっかりとした研修時間を確保するため |
1860時間 |
|
C-2 |
高度技能研修者の医療機関 |
高度な技能を身につけるため |
1860時間 |
※参考文献「医師の時間外労働時間の上限について 〜A・B・C水準とは〜 | 日本産婦人科医会|産婦人科医の働き方改革 」
上記の表のように、医療機関によって時間外労働の上限が規制されることで、長時間にわたる労働が出来なくなりました。
働き方改革後に、上記の時間外労働の上限を超えてしまうと罰則になる場合があります。
そのため、医療機関で働く際にはしっかりと水準について把握しておくことが大切です。
1-1-2:連続勤務時間制限と勤務間インターバル・代償休息
医師の医療現場での労働時間は長時間になりがちですが、十分な休息を取らずに働き続けると、医師の健康を害するばかりでなく、医療の質の低下にもつながりかねません。
そこで、次の3つの追加的健康確保措置が設けられました。
この措置は、A水準では努力義務とされている一方、B水準とC水準では義務とされています。
1、連続勤務時間制限
連続勤務時間制限として、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除いて、28時間までが限度となります。
2、勤務間インターバル
勤務間インターバルとして、当直及び当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間の連続した休息時間を確保することが求められます。
当直明けの日は、宿日直許可があるかどうかにより異なります。
宿日直許可がある場合は、通常の日勤と同様、9時間の勤務間インターバルが必要です。
宿日直許可がない場合は、連続勤務時間制限を28時間とした上で、18時間の勤務間インターバルが必要になります。
3、代償休息
予定された9時間または18時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由により緊急対応として業務に従事した場合に、従事した時間分の休息を事後的に付与することです。
代償休息は、疲労回復に効果的な休息の付与することが目的であるため、次の点に留意すべきとされています。
- 睡眠の量と質の向上につながるものになること。
- 代償休息を生じさせる勤務後にできる限り早く付与すること。
- オンコールからの解放など仕事から切り離された状況を設定すること。
1-1-3:月60時間を超える時間外割増賃金率の引き上げ
医師の働き方改革において、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが行われます。
これは、医師が過度の時間外労働を行っているにもかかわらず、それに見合った残業代が支払われていないケースが多い、という課題に対処するための重要な措置です。
具体的には、月60時間を超える法定時間外労働に対して、雇用者は「50%以上の割増賃金率」を算出して支払うように求められます。
医療法人や個人開業医などの場合も、「常時使用する労働者の人数」の規模に応じて大企業や中小企業と区分され、法定割増賃金率の引き上げが適用されます。
これにより、時間外労働に対して割増賃金が支払われることになり、医師への適切な報酬が期待されます。
ただし、労働時間管理を徹底し、医師側も積極的に時間外労働を申告する必要があります。
医師と雇用者双方が法定割増賃金率の遵守に努めることで、医師の健康と労働環境の改善が実現されるでしょう。
1-2:副業・バイト先での労働時間が制限される可能性がある
働き方改革制度後の勤務時間は、副業・アルバイトでの労働時間もカウントされます。
2024年4月以降は、「勤務先の水準を把握」「働いている時間を把握」の2点に気をつけて仕事をする必要があります。
なぜなら、「異なる医療機関で働く場合は、勤務時間を合わせて計算する」という決まりになっているからです。
しかし、さまざまな時間に、手術や検査といった仕事をしている医師は、自分自身が働いている時間を正確に把握することは困難です。
そのため、対策として、医師の勤務時間を正確に把握することが可能なICTを採用している医療機関も増えてきています。
1-3:宿日直許可がある副業・バイト先での勤務時間はカウントされない
宿日直の許可を取得するための基準は、労働基準法によって定められています。
以下の基準を満たしている医療機関においては、労働基準監督署の方から、「宿日直許可」を得ることができます。
- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもの
- 特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限る
- 宿直の場合は、夜間に十分睡眠が取りえること
- 上記以外の、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること
宿日直許可を取得している医療機関で働く場合においては、2024年4月から制定される時間外労働の上限規制の影響を受けずに、アルバイトをすることが可能です。
そのため、アルバイト先の時間外労働を抑えたいと思っている医師の方には、宿日直許可がある医療機関がおすすめです。
1-4:医師の労働時間の管理方法とペナルティについて
アルバイトの勤務時間の管理方法については、原則的に医師本人からの報告を基に、常勤先の医療機関が行います。
医師は、アルバイト先が宿日直許可を得ている医療機関かどうかを確認し、常勤先に医師本人が申告する必要があります。
そのため、医師は、本業やアルバイトでの労働時間をしっかり管理することが重要です。
時間外労働の上限を超えると、所属している医療機関にペナルティ、罰則が科される可能性があります。
罰則としては労働基準法第141条により、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。
ペナルティを受けるまでの 流れは以下の3つになっています。
- 労働基準監督署による調査
- 違反が認められた際には、是正勧告・改善指導
- 是正勧告を無視した場合は、法的な処分
このように、時間外労働の上限を超えてしまっても、直ぐに医療機関がペナルティをうけることはありません。
しかし、一度ペナルティを受けてしまった医療機関は、メディアで公表されるおそれがあるため、その医療機関の信用問題となり経営に大きな損害が出てしまいます。
そのため、医療機関は、勤務医師の時間外労働時間をしっかり管理し、常に把握しておく必要があります。
また、時間外労働の上限を超えてしまった場合には、労働監督署の指示に沿って手続きをする必要があります
2章:働き方改革による収入への影響
医師の働き方改革による収入への影響として、次の2つがあげられます。
- 医療機関による労働時間の管理と勤務体系の見直し
- 医師によっては副業・バイト先からの収入が減る可能性がある
それぞれ解説します。
2-1:医療機関による労働時間の管理と勤務体系の見直し
医師の働き方改革をスムーズに進めていくためには、医療機関による労働時間の管理と勤務体系の見直しが必須となります。
なぜなら、適切な労働管理システムが導入できなければ、これまで長時間労働が当たり前になっていた医師の労働時間を制限し、時間外労働の上限規制を超えることなく運営することが難しいからです。
医療機関では、医師や看護師などの医療従事者が、24時間365日人々の命と健康を守るために多様な勤務形態で働いています。
しかし、この多様性が逆に、医師や医療従事者の労働時間の実態を、正確に把握することを困難にしています。
特に医師の場合は、診察や治療だけでなく、診断書の作成や研修医への指導、臨床研究など、多くの業務を同時に遂行する必要があります。
また、一部の医療施設では、人手不足や勤怠管理の不備から、医師が連続して勤務するケースも多くあります。
これらの問題を解決するためには、適切な労務管理と勤務体系の見直し、医師それぞれの労働時間の把握、また必要な場合は医師の労働時間を制限することも必要となります。
2-2:医師によっては副業・バイト先からの収入が減る可能性がある
これまで勤務医としての収入だけでなく、副業・医師バイトで収入を得ていた医師にとっては、働き方改革によって収入が減る可能性があります。
なぜなら、医療機関による医師個人の労働時間管理が見直され、上限規制内の労働時間しか認められなくなるからです。
また先に解説したように、副業・アルバイト先での労働時間もカウントされるため、時間外労働の上限規制の範囲内での収入しか得られなくなります。
バイト先が宿日直許可を取得している医療機関であれば、労働時間はカウントされませんが、宿日直許可を取得している医療機関は限られているため、簡単には見つからない可能性があります。
現在、常勤先と異なる医療機関で、アルバイトをして収入を得ている医師は多いですが、働き方改革以降は、これまでのように自由にアルバイトができなくなり、バイト収入が減り年収が下がることが予想されます。
3章: 働き方改革で収入を確保するための対策
医師の働き方改革によってアルバイトが制限され、収入が減る可能性があります。
収入を確保するためには、以下の対策があります。
- 宿日直許可がある副業・バイト先を探す
- 転職や開業医を検討する
- フリーランス医師を目指す
それぞれ順番に解説します。
3-1:宿日直許可がある副業・バイト先を探す
働き方改革で医師バイトの収入を確保するためには、宿日直許可のある医療機関を探す必要があります。
なぜなら、宿日直許可がない副業先・アルバイト先での勤務を行うと、早い段階で時間外労働の上限規制を超えてしまうからです。
結果的に、アルバイトを減らしたり時間外労働減らす必要が出てくるため、収入が減ってしまいます。
そういった事態を防ぐためには、宿日直許可がある副業・バイト先をあらかじめ確保する必要があります。
3-2:転職や開業医を検討する
転職や開業を検討することは、収入を確保するために有効な手段です。
今よりも高収入で、勤務条件が良い病院へ転職すれば、収入アップを見込める可能性もあります。
また、開業することも有効な手段です。
しかし、市場調査や資金計画、立地選定など多くの準備が必要です。
医療機器の購入やスタッフの作用、診療所の運営に関する知識も必要で十分な計画が必要になります。
しかし、うまく集患し経営が軌道に乗れば、勤務医では実現が難しい高収入も実現できます。
3-3:フリーランス医師を目指す
フリーランス医師の働き方は大きく分けて4つあり、それぞれ特徴も異なります。
- 定期非常勤
- スポット
- 定期非常勤+スポット
- 臨床以外のアルバイト・パート
働き方と特徴をそれぞれ詳しく解説していきます。
定期非常勤
定期非常勤とは、働きたい日にちや時間を事前に決めて、定期的に出勤する働き方です。
比較的安定した収入が期待でき、常勤よりも勤務時間が短いことが特徴です。
また、時間外勤務やオンコールも基本的にないため、自分の時間を大切にしたい方にもおすすめな働き方です。
複数の医療機関を掛け持ちして働くことも可能なので、さまざまな医療機関の業務に携わることも可能です。
スポット
スポットとは、日雇いのアルバイト・パート勤務のことです。
1日だけ、数時間だけといった形態で単発契約を結ぶので、スケジュールを自由に選定できる特徴があります。
また、常勤医師が不在になっている際に、代わりの医師として働くことが多いので、高い技術力を持っている分、給料は高いです。
定期非常勤+スポット
定期非常勤+スポットとは、定期非常勤として定期的に出勤しながら、空いている日にちや時間にスポット勤務として働くことです。
短い時間で安定した収入を確保しながら、高い収入を得ることが出来る特徴があります。
そのため、効率よく稼げる勤務方法となります。
臨床以外のアルバイト・パート
臨床以外のアルバイト・パートとは、臨床を離れていても商品開発や記事作成などの分野で高い知識を活かして高収入で働くことです。
医療機関以外にも、医師のスキルを求めている企業は多くあるので、医師監修の需要は高くなっています。
フリーランス医師として働くメリットは、以下の3つです。
- 自分に合った働き方が可能
- 高収入が期待できる
- 人脈が広がる
それぞれのメリットを詳しく解説していきます。
自分に合った働き方が可能
自分に合った働き方が出来るのが、フリーランス医師の一番のメリットになります。
定期非常勤やスポットなどの、自分の都合に合わせて働く日にちや時間を決めることが可能です。
そのため、育児や介護などの家庭の事情で長時間勤務が困難な方でも、安心して働くことができます。
高収入が期待できる
定期非常勤やスポット勤務は、高い技術力を求められているので、貰える収入も高く設定されています。
また、複数の医療機関で掛け持ちも可能なため、効率よく働くことが可能です。
そのため、高収入が期待できる働き方になっています。
人脈が広がる
フリーランス医師は常勤医師と違い、さまざまな医療機関で働くことが多いので、その分人脈が広がるメリットがあります。
また、仕事の幅が広がる、人と会話する技術が身につく、さまざまな医師の技術を見ることが出来る、などのメリットもあります。
フリーランス医師には、多くのメリットがある代わりにデメリットも存在しています。
フリーランス医師のデメリットは以下の2つです。
- 安定性が低い
- 個人の責任や負担が大きい
それぞれのデメリットを詳しく解説していきます。
安定性が低い
フリーランス医師として働く際の、一番のデメリットは安定性が低いことです。
定期非常勤は、ある程度安定はしていますが、取引先の医療機関から急に仕事を打ち切られる可能性もあります。
また、常勤医師と違い、自身が病気になった際の福利厚生がないため、休業手当などの保障を受けることは出来ません。
個人責任や負担が大きい
フリーランス医師は個人事業主なので、仕事をしていく上での責任は全て自分で負うことになります。
仮に医療事故などのトラブルが起きた際でも、病院の後ろ盾がないため、多額の賠償金を支払うことになるケースもあり注意が必要です。
また、経費や税金・保険料などの負担が大きいこともデメリットの一つです。
まとめ:医師の働き方改革によるバイトや収入への影響
最後に、もう一度この記事の内容をおさらいしましょう。
医師の働き方改革における3つのポイント
- 勤務医の時間外労働は原則「960時間以下」
- 連続勤務時間制限と勤務間インターバル・代償休息
- 月60時間を超える時間外割増賃金率の引き上げ
働き方改革の「時間外労働の上限規制」により、医師バイトに出る4つの影響
- 時間外労働に上限規制が適用される
- 勤務時間は、副業・アルバイトでの労働時間もカウントされる(宿日直許可を取得している医療機関はカウントされない)
- 時間外労働の上限を超えてしまったら、所属している医療機関にペナルティが課せられる
- 非常勤先からの収入が減り、年収が下がる
働き方改革が発令されても年収が下がらないようにする対策
- 宿日直許可のある医療機関でアルバイトをする
- 転職や開業医を検討する
- フリーランス医師を目指す
フリーランス医師の働き方4種類
- 定期非常勤
- スポット
- 定期非常勤+スポット
- 臨床以外のアルバイト・パート
フリーランス医師のメリット3種類
- 自分に合った働き方が可能
- 高収入が期待できる
- 人脈が広がる
フリーランス医師のデメリット2種類
- 安定性が低い
- 個人の責任や負担が大きい
この記事の内容をしっかりと理解して、あなたにとってベストな働き方をしましょう。