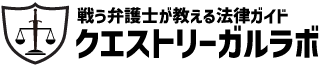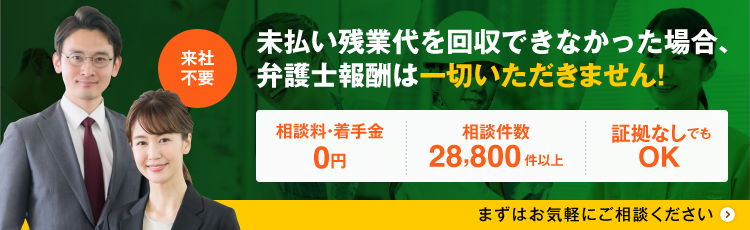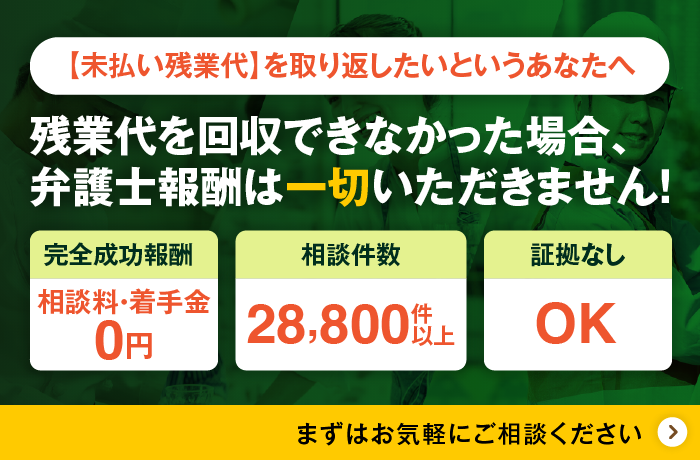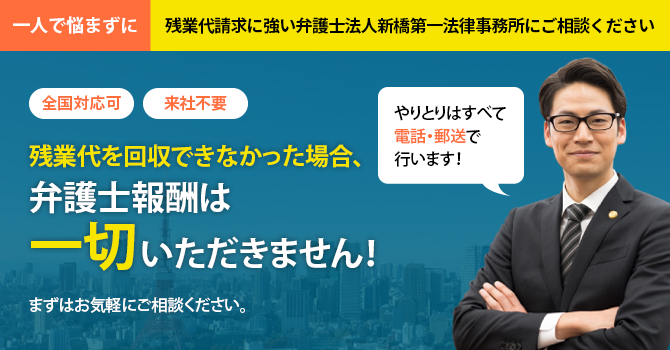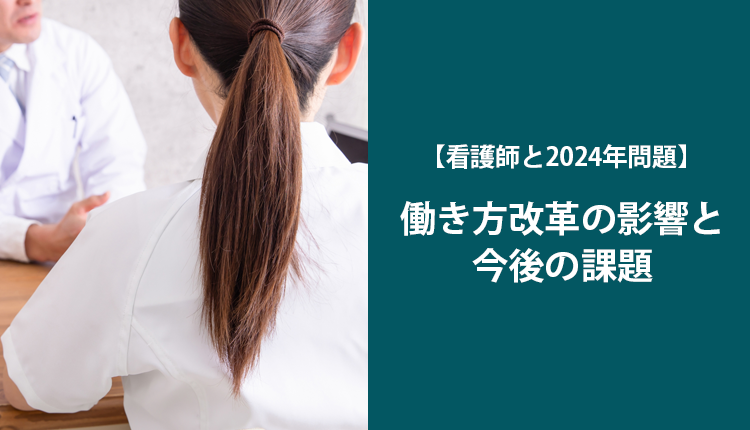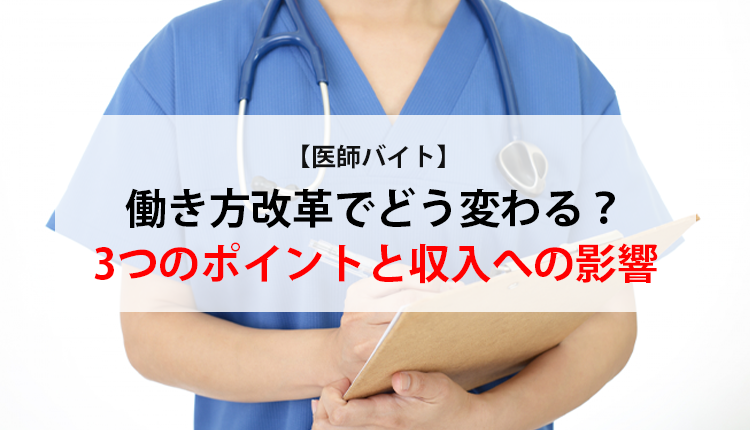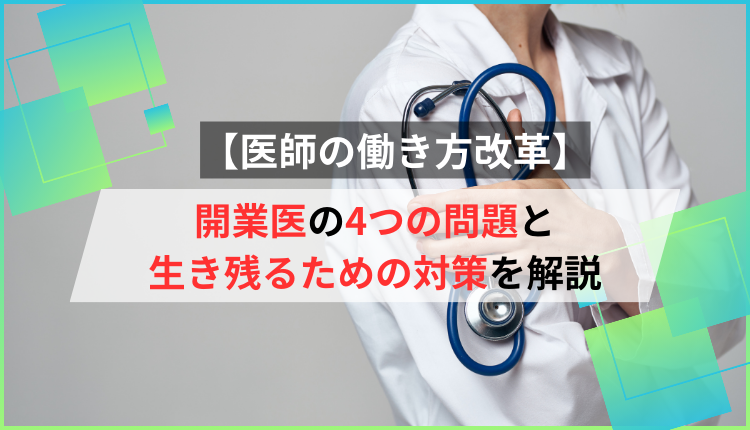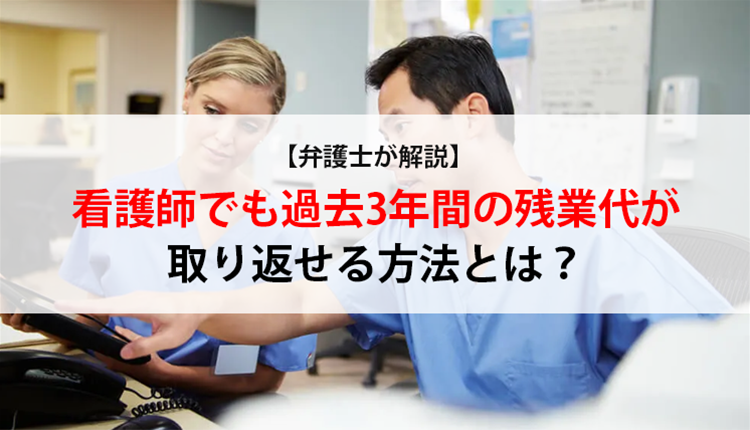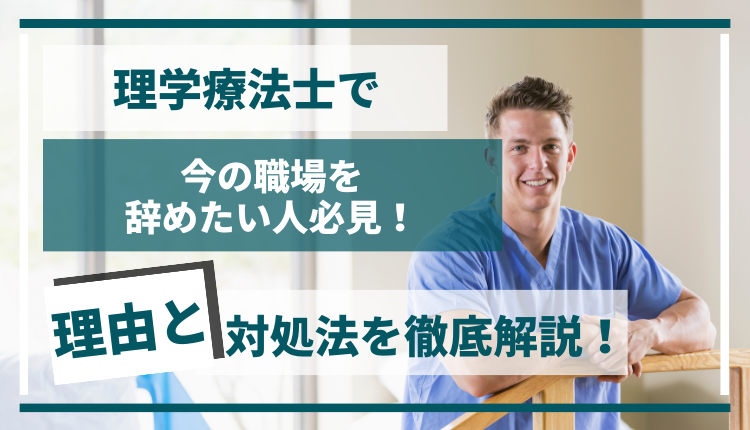看護師は働き方改革でどう変わる?4つのポイントと看護師への影響
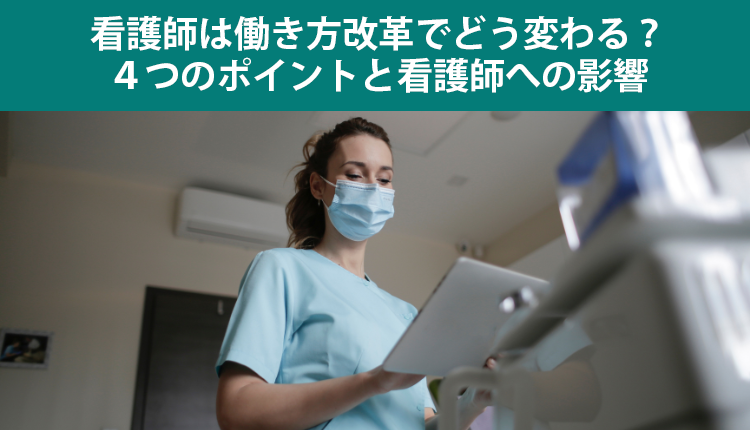
この記事を読んで理解できること
- 看護師の働き方改革の4つのポイント
- 医師の働き方改革による看護師への影響
- 看護師の働き方改革の実態
あなたは、
- 看護師の働き方改革とは、どんな内容なの?
- 医師の働き方改革で、看護師の仕事が増えるのでは?
- 看護師の働き方の実態は?
などといった疑問をお持ちではないでしょうか。
看護師の労働環境の現状は課題が多く、時間外労働やサービス残業、過酷な夜勤などが原因で、離職する看護師も少なくありません。
そこで、日本看護協会は国の「働き方改革」を受けて、
「働き続けられる仕組みをつくる。その仕組みは実現可能で、持続可能な仕組みであること、看護職が生涯にわたって、安心して働き続けられる環境づくりを構築し推進する」
と、看護師における働き方改革の目標を掲げています。
しかし、働き方改革によって看護師の労働環境がどのように変わっていくのか、知らない方も多いのではないでしょうか。
職場環境の改善を進めていくうえで、看護師一人ひとりが働き方改革について知ることは重要です。
そこでこの記事では、
1章では、看護師の働き方改革の4つのポイントを
2章では、医師の働き方改革による看護師への影響を
3章では、 看護師の働き方改革の実態
について解説します。
「看護師の働き方改革」は、看護師のこれからの働き方を考えるうえで重要な改革です。
自分らしく、専門職として自立した働き方ができるように「看護師の働き方改革」について知りましょう。
1章:看護師の働き方改革の4つのポイント
病院やクリニックなど大小問わず、すべての医療機関で行われる看護師の働き方改革のポイントを、4つ紹介します。
- 時間外労働に罰則付き上限規制が適用される
- 有給休暇年5日以上の取得が義務付けられている
- 労働時間の記録が義務付けられている
- 同一労働同一賃金が適用される
それぞれ詳しく解説します。
1-1:時間外労働に罰則付き上限規制が適用される
1つ目のポイントは、「時間外労働の罰則付き上限規制の導入」です。
|
時間外労働の上限 |
原則として月45時間、年360時間 |
|
特別な事情があり、 上記の時間を超える場合 |
年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む) 月100時間未満(休日労働を含む) |
上記の範囲内で、労働基準法36条に基づく労使協定である「36協定」を締結します。
時間外労働を減らすことは、看護師の負担を軽くするためには重要です。
看護師の負担を軽くすることで、質の高い看護ケアの提供にもつながります。
下記の時間も労働時間に含まれます。
自分の職場で、きちんと時間外労働として認められているか確認してください。
- 業務として参加を指示された研修会や勉強会
- 指示による自己学習
- 情報収集など業務の準備・後始末
- ユニホームへの更衣 など
新人時代に業務後に研修を受けたり、指導を受けたりした経験がある看護師も多いのではないでしょうか。
試用期間中の新人看護師であっても、研修や指導を受けている時間は業務時間になります。
一人前ではないからなどという理由で、時間外労働が認められない場合は、違法になります。
1-2:有給休暇年5日以上の取得が義務付けられている
2つ目のポイントは、「年5日以上の有給休暇の取得の義務付け」です。
職場は、年10日以上の有給休暇を付与された看護師には、年5日の有給休暇を取得させなくてはなりません。
取得日は、看護師本人の希望を聞き管理者が指定します。
有給休暇を取得するために、職場は下記のような取り組みが必要です。
- 各部署で年次有給休暇取得の計画を立てる
- 有給休暇取得できるように人員配置する
- 有給休暇申請の方法を再確認する など
「夏季休暇」が就業規則で所定休日の場合、夏季休暇は有給休暇に含まれません。
勤務先の就業規則を確認し、有給休暇を取得できているか知っておきましょう。
有給休暇の取得は、看護師のワークライフバランスの推進に重要です。
看護師として働き続けながら、プライベートも充実した働き方を実現しましょう。
1-3:労働時間の記録が義務付けられている
3つ目のポイントは、「労働時間の記録の義務付け」です。
タイムカードや電子カードなどによる方法で、正確な勤務時間の把握が必要となります。
出勤や退勤の時刻が記載されていない押印方式の出勤簿は、出勤時間や退勤時間がきちんと把握されにくいため、サービス残業などが日常的になりやすいです。
働く職場で、労働時間が正確に把握されているか確認してください。
1-4:同一労働同一賃金が適用されるなりや
4つ目のポイントは、「同一労働同一賃金」の適用です。
正社員や契約社員、パート、アルバイトなど看護師の雇用形態はさまざまです。
同じ業務をしているにも関わらず、給与に大きく差があることも少なくありません。
理不尽な待遇差を解消し、看護師がどの雇用形態を選んだとしても、納得して働けるルールとして整備されたのが「同一労働同一賃金」です。
同じ労働に対しては、同一の賃金が支払われる必要があります。
自分の労働に対して、適切に賃金が支払われているか確認してみましょう。
2章:医師の働き方改革による看護師への影響
医師の働き方改革は、2019年から順次施行されています。
医師の働き方改革による看護師への影響について、ここでは下記の2つを取り上げます。
- タスクシフトで看護師の仕事が増える可能性がある
- 看護師の負担を増やさないため業務内容が見直される
それぞれ解説します。
2-1:タスクシフトで看護師の仕事が増える可能性がある
医師の業務のタスクシフトで、看護師の仕事が増える可能性があります。
タスクシフトとは、医師の業務の一部を看護師や薬剤師など他の職種に移管することです。
2024年4月からの働き方改革で、時間外労働の上限規制が医師にも適用されます。
そのため、医師が行っている業務の一部を、看護師や医師事務作業補助者などの他職種へ、移管するための環境が整備されてきました。
看護師へタスクシフトが推進されている主な業務は、下記のとおりです。
- 特定行為(38行為21区分)
- 薬剤の投与
- 採血
- 血液検査オーダー入力
- 血管造影検査などの検査・治療の介助
- 注射・ワクチン接種
- 静脈採血
- 静脈路確保・抜去及び止血
- 末梢留置型中心静脈カテーテルの抜去及び止血
- 動脈ラインからの採血、動脈ラインの抜去及び止血
- 予診・検査説明
- 同意書の受領
- 尿道カテーテル留置
上記のような業務を、今後看護師に移管される場合もあるため、看護師の仕事量がさらに増える可能性があります。
2-2:看護師の負担を増やさないため業務内容が見直される
医師の業務のタスクシフトによって、看護師の負担を増やさないように、業務内容を見直すことも必要です。
医師の業務負担を減らすことは重要ですが、看護師の業務が増え負担になることは、看護師の働き方改革になりません。
看護師の負担を軽減するために、看護師の業務を薬剤師や看護補助者などの他職種へ、タスクシフトする必要もあるでしょう。
そのため、看護師のタスクシフトの推進に、「看護補助者の活用」が重要です。
2022年の診療報酬改定で、看護師の負担を軽減する目的で、「看護補助体制充実加算」が新設されました。
医師からのタスクシフトで業務量が増え、多忙な看護師の負担を減らし、看護補助者がスキルを磨く環境を整えるための加算です。
看護師が行う業務の一部を、看護補助者にタスクシフトすることで、看護師の負担を減らすことが重要です。
3章: 看護師の働き方改革の実態
看護師の働き方の実態は、下記のとおりです。
- 看護師は残業・夜勤が多い
- 暴力・ハラスメントにあう場合もある
- 仕事を自分でコントロールしづらい
- 業務に変化が少なくキャリアアップしづらい
看護師の働き方改革を理解するために、看護師の労働環境の実態についても知っておきましょう。
3-1:看護師は残業・夜勤が多い
看護師は、残業や夜勤が多い職業です。
日本看護協会が行った「2022年病院看護・助産実態調査」によると、1人あたりの月平均超過勤務の時間は「1〜4時間未満」が最も多く、全体の31.7%でした。
さらに、4時間以上超過勤務している看護師は52.8%にもおよび、中には20時間以上の方もいます。
また、1人当たりの月平均の夜勤回数(二交代制)は、およそ6割が4〜6回未満と回答しています。
上記の実態を踏まえ、ここでは、
- 看護師は残業が多い原因
- 夜勤による負担が大きいこと
について紹介します。
看護師を疲弊させている、残業や夜勤の実態について知っておきましょう。
以下でそれぞれ説明します。
3-1-1:看護師は残業が多い原因
看護師は仕事の特性上、残業が多くなりがちです。
看護師の残業となる原因の業務は、以下のとおりです。
- 次の勤務者への引継ぎ
- 看護記録や看護サマリーの作成
- 患者の急変の対応 など
看護師の労働環境の実態として、上記の業務をしなければいけない環境にあるため、残業が多くなります。
そのため、業務時間内に引継ぎや記録ができるように、業務改善をすることが必要です。
残業により看護師が疲弊することで、看護の質の低下につながる可能性もあります。
患者様のためにも、看護師の残業時間の短縮が重要です。
3-1-2:夜勤の負担が大きい
夜勤の負担を大きく感じている看護師は、少なくありません。
二交代制をしている医療機関での夜勤時間は、平均で16時間です。
日勤に比べ夜勤では、勤務する看護師の数が少ないため、患者様の状態によっては休憩時間をとれないこともあります。
また、夜勤が難しい子育て中の看護師に夜勤を強いる、夜勤に入れないことでペナルティがあるという医療機関もあります。
そのため、夜勤をすることで看護師は負担を感じてしまうのです。
看護師は、女性が多く占めています。
結婚や出産、子育てなどによって、ライフスタイルが大きく変化する中で、ワーク・ライフ・バランスのとれた柔軟な働き方を実現することが今後の課題でしょう。
3-2:暴力・ハラスメントにあう場合もある
「保健医療分野における職場の暴力に関する実態調査」によると、暴力やハラスメントを受けたことがある看護師は少なくありません。
看護師は、患者様に接する時間が長いことからも、暴力やハラスメントにあうことが多いようです。
ふだんは温厚な患者様でも、病気の不安や痛みによって暴力的に行動することがあります。
患者様の思いに寄り添いたいという看護師の使命感から、暴力やハラスメントを受けても「病気だからしょうがない、自分のケアが不十分だから」などと考え、暴力やハラスメントに対応してしまいます。
しかし、暴力やハラスメントに対しては、組織的な対策が必要です。
組織が作成するマニュアル等を理解して、看護師全員が対策について知っておくことが重要となります。
3-3:仕事を自分でコントロールしづらい
看護師は、コントロール感をもって仕事しにくい環境にあります。
取り組まなければいけない業務があっても、自分で見通しや段取りをもち、調整しながら仕事に取り組むことが「仕事のコントロール感」です。
仕事をコントロールしながらできることは、やりがいや達成感につながるため、看護師が仕事を続けるためには重要なポイントです。
そのため、看護師も「仕事のコントロール感」を持てるような、職場環境がつくられることが大切です。
3-4:業務に変化が少なくキャリアアップしづらい
看護師は、業務に変化がなくキャリアアップしづらい実態があります。
自分の仕事が適切に評価されず、不満を持っている看護師も少なくありません。
勤務年数だけが理由でリーダーや役職に昇格し、きちんと能力を評価されない職場は、看護師の離職につながります。
そのため、クリニカルラダーなどの評価指標を導入し、能力に合った役割や責任を与え、適切な処遇が与えられることが大切です。
まとめ
最後に、本記事の内容をまとめます。
看護職の働き方改革の4つのポイント
- 時間外労働に上限規制が設けられ、違反した場合は罰則がある
- 年に5日の有給休暇の取得が義務付けられている
- 労働時間の記録が義務付けられている
- 同一労働に同一賃金が適用される
医師の働き方改革による看護師への影響
- 医業のタスクシフトで看護師の仕事が増える可能性がある
- 看護師の負担を増やさないため業務内容が見直される
看護師の働き方の実態
- 看護師は残業や夜勤が多い
- 暴力・ハラスメントにあう場合がある
- 仕事を自分でコントロールしづらい
- 業務に変化がなくキャリアアップしにくい
組織は「就業継続が可能な看護職の働き方」を実現するために、規則など整備していく必要があります。
また、看護師一人ひとりも働き方改革について理解し、行動していくことが重要です。
これからは看護師も、働き方改革によって、ワーク・ライフ・バランスを実現し、やりがいを持って働き続けていきましょう。