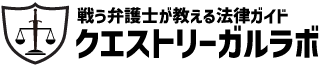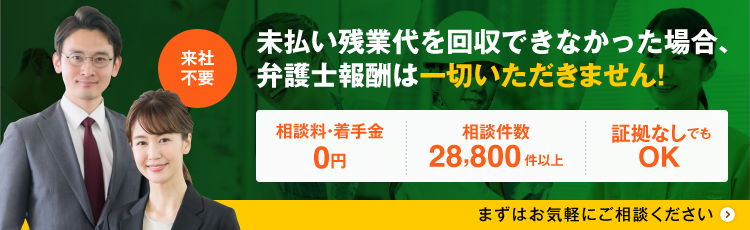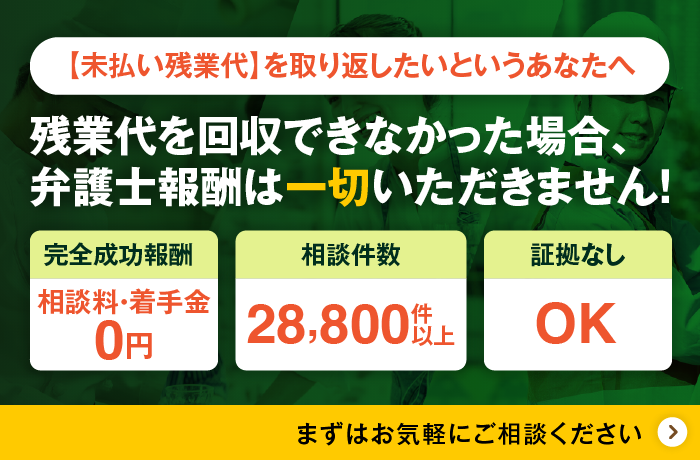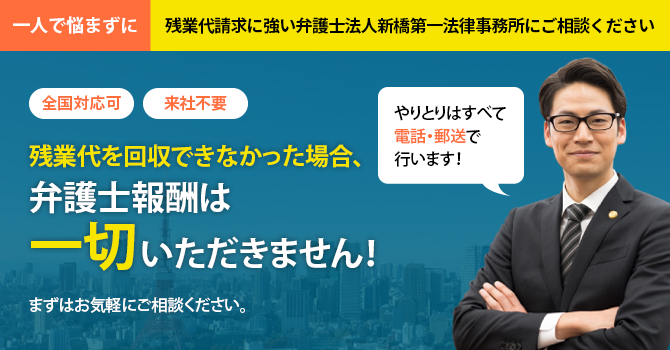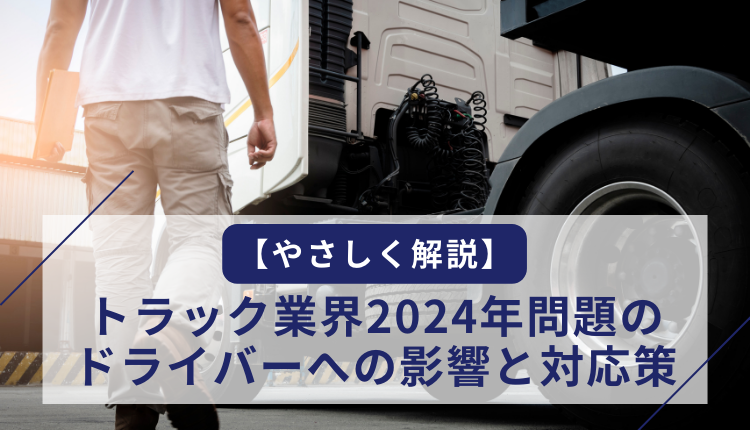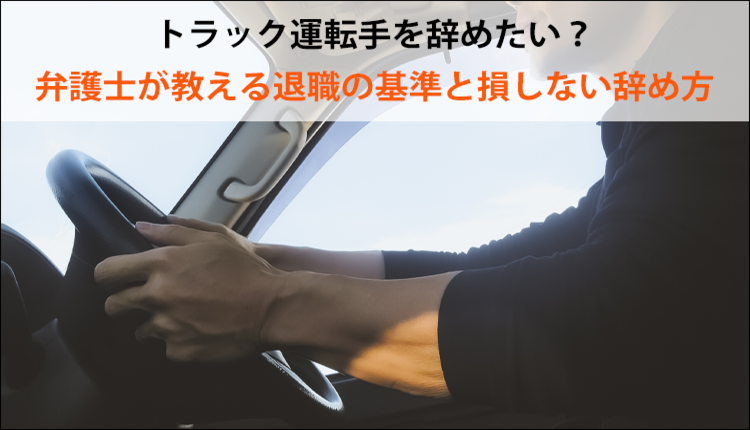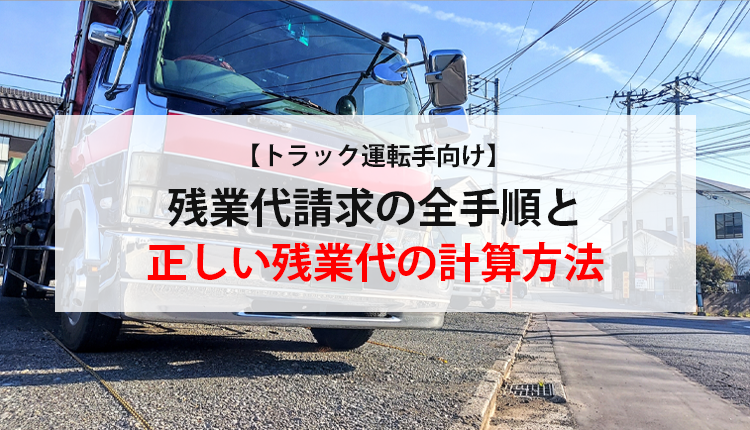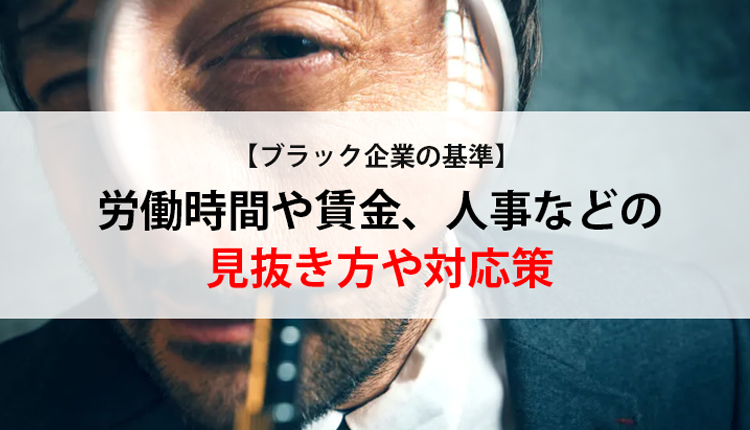【トラック運転手向け】運送業の労働時間の新ルールと違法な場合の対処法

この記事を読んで理解できること
- 運送業の労働時間の実態
- 運送業の労働時間の法的なルール
- 運送業の労働時間が上限を超えた場合のリスク
- 労働時間が違法な場合の3つの対処法
あなたは、
- 運送業の労働時間の実態が知りたい
- 運送業の労働時間の上限を知りたい
- 運送業で未払い残業代を請求したい
などとお考えではないですか?
運送業の労働時間の実態として、厚生労働省の令和4年の調査では、1か月の平均労働時間は206時間となっています。※
同じ調査では、調査産業計の1か月の平均労働時間は177時間となっているので、運送業の方が29時間も長くなっています。
運送業の労働時間が長くなりがちな理由は、運送業界の特徴として、短納期の仕事が多く、かつ荷待ち時間が長いからです。
そのため、運送業の時間外労働の見直しとして、令和6年4月1日から「年960時間(休日労働含まず)」の上限規制が適用されます。
これは「物流の2024年問題」と言われ、トラック運転手の労働時間が減り収入が減ってしまったり、輸送能力が不足する可能性が懸念されています。
そのため、違法に労働させられることがないよう、ルールを正しく把握し、未払い残業代は請求するなど、適切な対処を行うことが重要です。
そこでこの記事では、
1章では運送業における労働時間の実態、
2章では運送業の労働時間の法的なルール、
3章では運送業の労働時間が上限を超えた場合のリスク、
4章では労働時間が違法な場合の3つの対処法
を解説します。
この記事をしっかり読んで、運送業の労働時間に関する実態やルールを把握し、未払残業代がある場合は請求しましょう。
目次
1章:運送業の労働時間の実態
運送業の労働時間の実態として、次の2つがあげられます。
- 運送業(トラック運転手)の労働時間は平均206時間
- 運送業の労働時間が長くなる理由
それぞれ解説します。
1-1:運送業(トラック運転手)の労働時間は平均206時間
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、運送業(トラック運転手)の1か月の平均労働時間は206時間となっています。
これは、調査産業計の1か月の労働時間177時間より29時間も長くなっています。
次に、厚生労働省による毎月勤労統計調査を見てみましょう。令和5年6月分結果確報では、以下のようになっています。
【運輸業, 郵便業】
- 月間実労働時間:170.7時間
- 所定内労働時間:148.8時間
- 所定外労働時間:21.9時間
- 出勤日数:20.0日
【調査産業計】
- 月間実労働時間:142.4時間
- 所定内労働時間:132.4時間
- 所定外労働時間:10.0時間
- 出勤日数:18.5日
この調査によると、「運輸業, 郵便業」は、月間実労働時間で28.3時間、所定外労働時間(残業時間)で16.4時間、出勤日数は1.5日、それぞれ調査産業平均より多くなっています。
1-2:運送業の労働時間が長くなる理由
運送業の仕事でこれほど残業時間が長くなるのは、会社の方針という問題だけでなく、業界全体の体質や慣例が関わっています。
具体的には、次のような点が運送業の特徴です。
- 即日、短納期での配達が求められる
- 荷待ち時間がある
- 運転手の人手不足
それぞれ解説していきます。
■即日、短納期での配達が求められる
運送の現場では、短納期、場合によっては即日配達を依頼されるケースがあります。
実際、Amazonでは、当日お急ぎ便というものがあり、即日配達は珍しいものではなくなっています。
■荷待ち時間がある
また、荷待ち時間があることも、残業時間が長引く要因の一つです。
荷待ち時間とは、トラック運転手の業務時間中に手が空いたものの、労働から完全に離れず待機している時間のことです。
拘束されている待ち時間ともいえます。
令和3年の国土交通省の調査※によると、1運行における拘束時間は、「荷待ち時間がない運行(全体の 76%)」の平均拘束時間は10時間38分、一方「荷待ち時間がある運行」の平均拘束時間は12時間 26分となっています。
荷待ち時間があることで、1時間48分も拘束時間が長くなっています。
急ぎの配達が多くありながら、荷待ち時間もあり、これが残業時間を長くする要因となっています。
■運転手の人手不足
運転手の人手が足りていないことも、労働時間を長くする一つの要因です。
全日本トラック協会のWebサイトによれば、令和5年4月時点での「貨物自動車運転者」の有効求人倍率は「2.11」で、これは全職業の平均有効求人倍率「1.13」のほぼ2倍に相当します。
有効求人倍率は、求人数を求職者数で割る数値です。
この数値が高いほど、企業が積極的に雇用を進めている状態といえます。
「貨物自動車運転者」は、他職種の約2倍、企業が人材を欲していると言えます。
実際、運送会社の中で人手不足を感じる企業の数が急増しています。
特に、令和4年4月から6月までの期間において、トラック運転手の不足を実感している企業の割合は次の通りです。
- 運転手が不足している:7%
- 運転手がやや不足している:9%
つまり、6割以上の運送会社がトラック運転手の不足に直面しています。
そのため運送会社は、配送業務の際に運転手が不足する場合、それぞれ対応策が必要となります。
令和3年の「トラック輸送状況の実態調査結果」によれば、ドライバー不足時の対応策として、「ドライバーの早出残業で対応」や「ドライバーの休日出勤で対応」という選択肢が、平成27年調査時と比べ増加しています。
運転手の人手不足が、トラック運転手の労働時間が長くなる理由の一つとされています。
2章:運送業の労働時間の法的なルール
運送業の労働時間の法的なルールについて、ここでは次の2つを取り上げます。
- 運送業の労働時間の特徴
- 運送業の労働時間の上限
それぞれ解説します。
2-1:運送業の労働時間の特徴
労働時間に関するルールに『労働基準法』があります。
さらに、自動車運転者の労働時間については、『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』に定められる追加ルールもあります。それぞれの時間についてみていきましょう。
■労働時間
賃金の対象となる時間です。
労働時間は、労働契約(雇用契約)で明示されます(労働基準法第15条第1項)。
また、労働時間の上限は原則1日8時間、1週で40時間となっています。
運送業の労働時間は、令和6年3月末まで時間外労働の上限規制の適用が猶予されるため、上限規制を超える長時間労働が認められます。
令和6年4月1日からは、トラックドライバーの時間外労働の上限が、特別条項付き36協定を締結している場合でも「年960時間」となります。
■休憩時間
労働時間の途中にある時間で、労働者が自由に利用できる時間です(労働基準法第34条第1項、第3項)。
運送会社の中には、荷待ち時間を休憩時間とすることで、労働時間としてカウントしない場合があります。
■拘束時間
労働者が会社に拘束されている時間です。
労働時間、休憩時間、荷待ち時間で構成されます。
■休息期間
会社の拘束を受けない時間です。
勤務と次の勤務の間に、運転手の自由な生活時間として休息期間が定められています。
完全オフの時間というイメージです。
拘束時間と休息期間は、令和6年4月からの時間外労働の上限規制の適用に合わせて、長時間労働・過重労働を防ぐための改善基準告示の見直しが行われました。
上記4つの時間のうち、賃金の支払い対象は、労働時間のみとなります。
2-2:運送業の労働時間の上限
令和6年3月31日までの、労働時間の上限に関するルールを見ていきましょう。
|
1年、1か月の拘束時間 |
1か月293時間以内 ※労使協定により延長可能(1年3,516時間以内で1か月320時間以内を年6回まで) |
|
1日の拘束時間 |
原則13時間以内 ※上限16時間、15時間超えは週2回まで |
|
休息期間 |
1日継続8時間以上 |
2-3:令和6年4月1日からの労働時間の上限
令和6年4月1日より、労働時間の上限に関するルールが改正されます。
|
1年、1か月の拘束時間 |
1年3,300時間以内 1か月284時間以内 ※労使協定により、所定の条件下で延長可能(1年3,400時間以内で1か月310時間以内を年6回まで) |
|
1日の拘束時間 |
原則13時間以内 (上限15時間、14時間超えは週2回までが目安) ※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続16時間まで延長可能 |
|
休息期間 |
継続11時間以上が基本で、9時間を下回らない ※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続8時間以上も可能 |
原則として、拘束時間は削減、休息期間は増加というルールになっています。
3章:運送業の労働時間が上限を超えた場合のリスク
運送業の労働時間が上限を超えた場合のリスクとしては、以下のようなものがあります。
- 事故が発生するリスク
- 過労死のリスク
- 残業代のトラブルが発生するリスク
それぞれ解説します。
3-1:事故が発生するリスク
運送業は、労働災害の発生件数が多い業界です。
厚生労働省の発表資料による令和4年の労働災害発生状況では、陸上貨物運送事業の労働災害データは次のようになっています。
■業種別死亡災害発生状況
第三次産業(商業・金融・通信等合わせたもの)、建設業、製造業についで4位、構成比は11.6%
■業種別死傷災害発生状況
第三次産業(商業・金融・通信等合わせたもの)、製造業についで3位、構成比は12.5%
陸上貨物運送事業の死傷者数は、事故の型別では「墜落・転落」が最多で、「動作の反動・無理な動作」、「転倒」と続いています。
トラック運転手の労働時間が上限を超えた場合は、心身ともに負担が大きくなるため、これらの労働災害が起こるリスクはさらに高まります。
3-2:過労死のリスク
労働時間が上限を超えた場合、過労死のリスクが高まります。
厚生労働省の『令和3年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況』には、
「令和3年度の脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数 172 件のうち 53 件が貨物自動車運転者に関するものであり、労災支給決定(認定)件数に占める割合が大きい。 このようにトラック運転者の長時間労働等の実態は深刻であり、その改善は急務である」
という記述があります。
3-3:残業代のトラブルが発生するリスク
運送業の労働時間が上限を超えた場合、残業代のトラブルが発生するリスクが高まります。
なぜならその会社は、ルールを超えた労働時間分の残業代を支払わない可能性があるからです。
法的に許されないことですが、実際の業務では上限を超えた労働をさせながら、残業代の対象となる労働時間を少なく算出する可能性があります。
そうすれば、表向きは労働時間に関するルールを守っていることになり、さらに残業代も浮くからです。
実際に働いた分の残業代が出ないのは嫌ですよね。
次の章では、残業代のトラブルや労働時間が違法な場合の対処法を解説します。
4章:労働時間が違法な場合の3つの対処法
労働時間が違法と分かった場合、3つの対処法を考えてみましょう。
- 労働基準監督署に相談する
- 優良な運送会社に転職する
- 弁護士に相談して残業代を請求する
それぞれ解説します。
4-1:労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に申告することで、会社に対して調査が行われ、違法状態を是正してもらえる可能性があります。
労働基準監督署は、厚生労働省の機関であり、全国に署があります。
「労基」と略されて呼ばれることもあります。
この労働基準監督署に「方面(監督課)」という課があります。
この課では計画的に、または働く人からの申告などを契機として、事業者の事務所に立ち入り、労働条件の確認を行います。
その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対して是正指導します。
4-2:優良な運送会社に転職する
労働時間が違法な場合は、労働基準法で定められた労働時間を、適切に管理する優良な運送会社に転職するのも一つの方法です。
ただし、入社前に案内された条件が、入社したら違っていた、という場合もあるので、慎重にコミュニケーションをとることも大切です。
4-3:弁護士に相談して残業代を請求する
実際の労働時間に対して、未払いの残業代がある場合は、弁護士に相談して残業代を請求する方法があります。
労働者が正当に受けるべき残業代が支払われていない状況は、法的に問題がある可能性があります。
運送業では、労働時間が長く給与体系も複雑なため、残業代をごまかされるケースがとても多いです。
拘束時間が長く、長時間の労働を強いられている場合は、請求することによって高額の残業代を取り返せる可能性があります。
まとめ:運送業の労働時間と上限規制
運送業の労働時間について正しい知識を身に着けることはできたでしょうか?
最後に、簡単に振り返ってみましょう。
■運送業の労働時間は、産業平均より長い
・運送業の労働時間が長くなる原因は、荷待ち時間、運転手の人手不足などにある
■運送業の労働時間に関するルールには、『労働基準法』や『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』などがある
・運送業の労働時間の上限に関するルールが、2024年4月1日から改正される
・改正ルールにおいては、基本的に、拘束時間の上限が減り、休息期間が増加する
■運送業の労働時間が上限を超えた場合のリスクとして、事故・過労死・残業代トラブルがある
・労働時間が違法な場合の対処法として、労働基準監督署への相談、優良運送会社への転職、弁護士相談のうえ残業代請求がある
この記事をしっかり読んで、適正なルールに基づいた、労働時間に見合った適切な賃金を受け取りましょう。