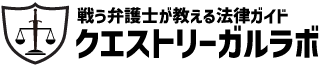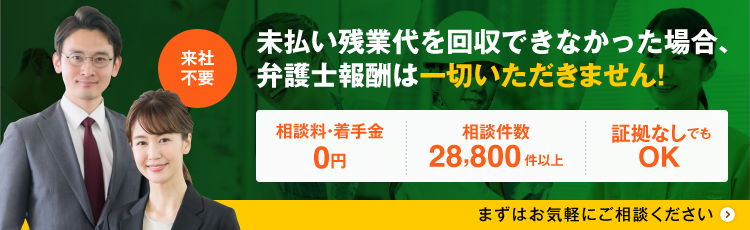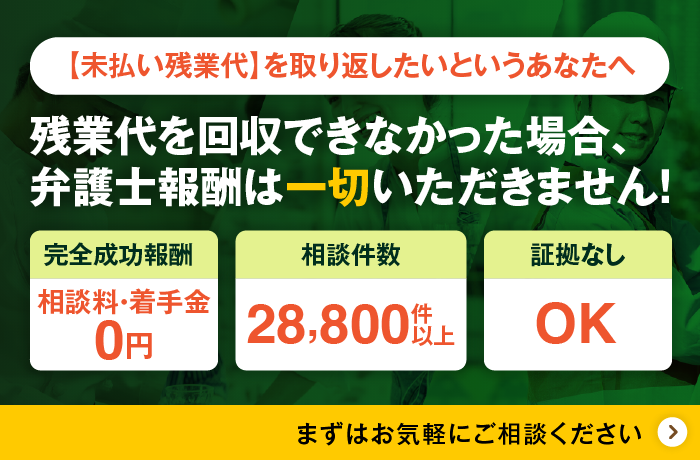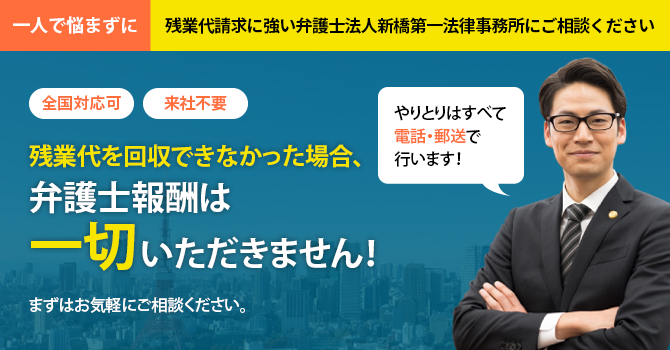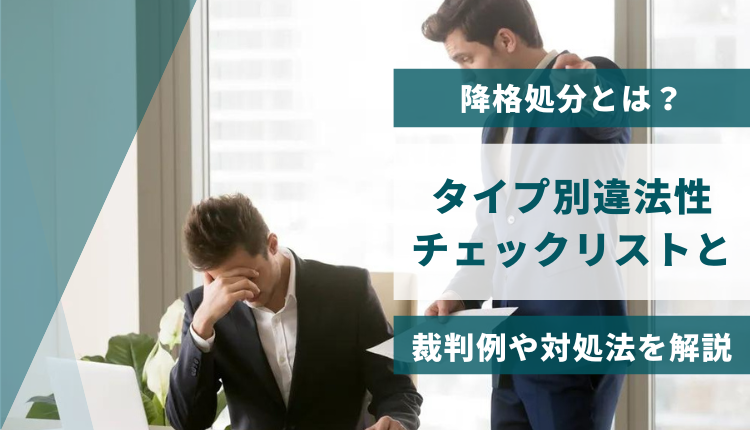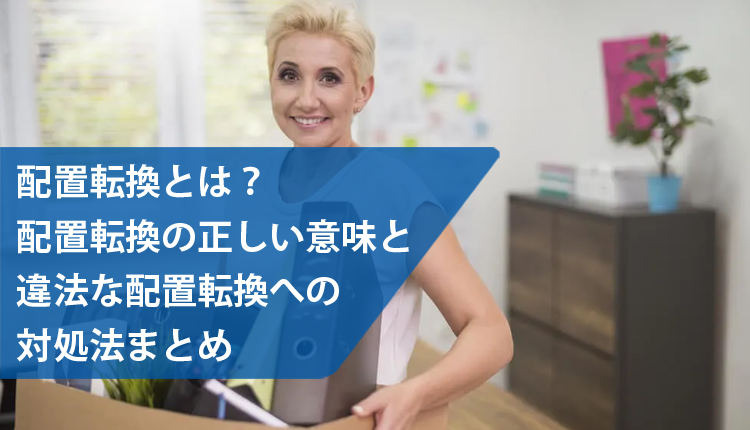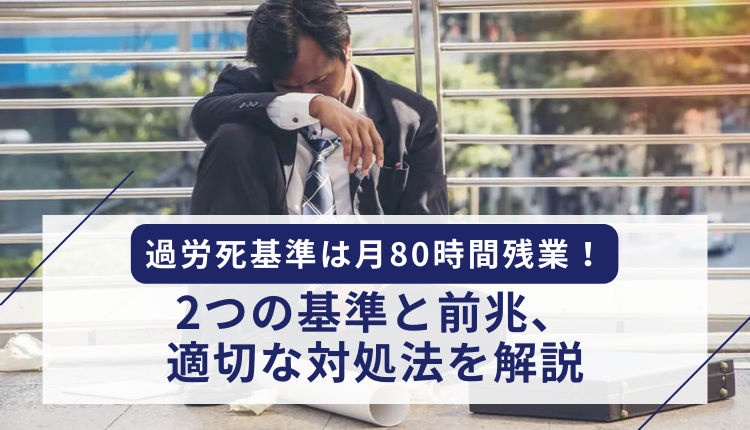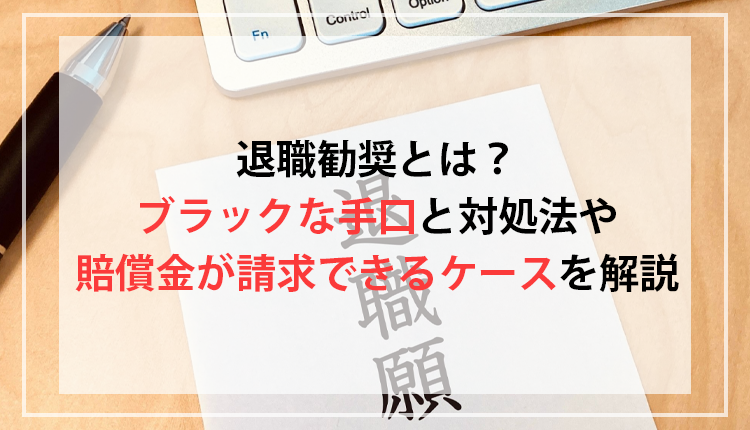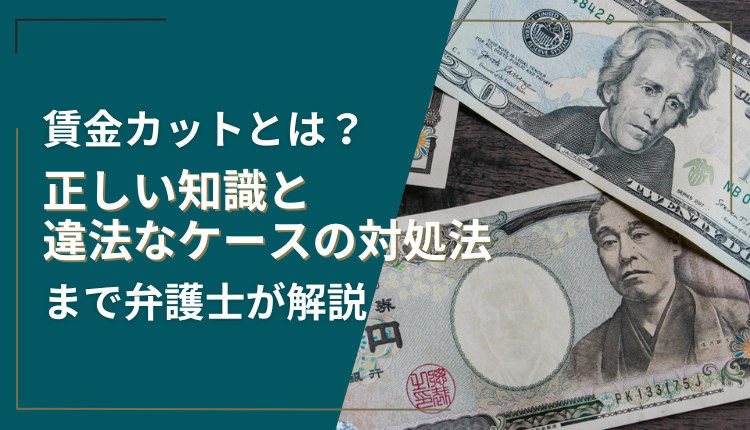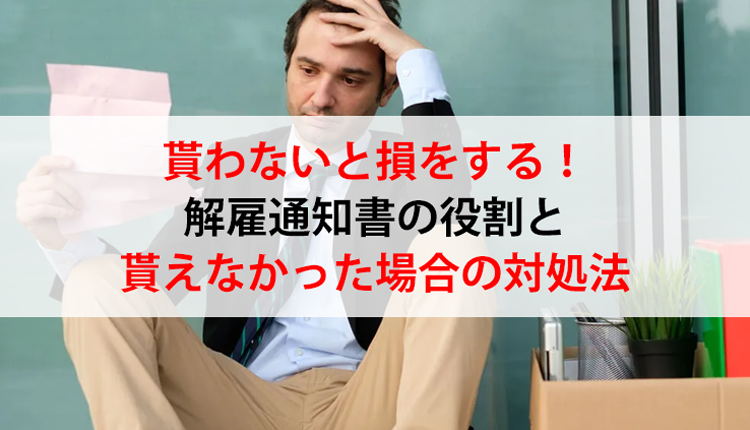- 更新日:2024.07.08
- #雇用契約書ない
【雇用契約書がない】労働条件の書面がない時のトラブルと対処法を解説
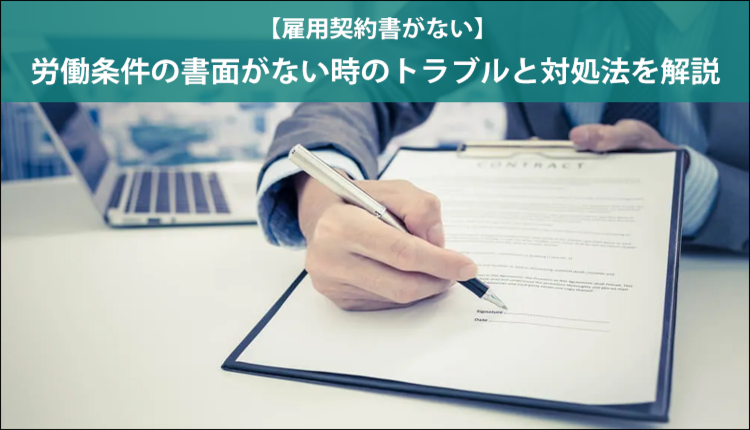
この記事を読んで理解できること
- 雇用契約書がないことは違法ではない
- 労働者に明示すべき労働条件
- 雇用契約書がない場合のありがちなトラブル
- 雇用契約書・労働条件通知書がない場合の対処法
あなたは、
- 会社に雇用契約書がないのは違法?
- 雇用契約書がないとトラブルになりそうで心配
- 雇用契約書がない場合はどうしたら良い?
などとお考えではないですか?
結論から言うと、法律上、雇用契約書は必ずしも必要というわけではないため、もしあなたの会社に雇用契約書がない場合でも違法ではありません。
労働契約法第6条:労働契約の成立
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
これにより、労働契約は、当事者である労働者及び使用者の合意があれば口頭でも契約は成立するため、契約内容について書面を交付することまでは求められていません。
しかし、労働基準法第15条1項では労働条件を明示しなければならないとされているため、労働条件通知書などを会社は交付して、労働者に労働条件を明示する義務があります。
労働基準法第15条1項:労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
したがって、
「自分の労働条件がどんなものか、労働条件を示す書面がない」
という場合は、違法である可能性が高いです。
さらに、雇用契約書は義務ではありませんが、労働条件や契約内容を労働者と会社が合意したことを証明するために、ほとんどの会社が活用しています。
そこでこの記事では、1章で雇用契約書と労働条件通知書について、2章では労働者に明示すべき5つの労働条件について解説します。
さらに、3章では雇用契約書がない場合のありがちなトラブルを、4章では雇用契約書・労働条件通知書がない場合の対処法について解説していきます。
この記事の内容をしっかり理解して、雇用契約で会社とトラブルにならないように注意してください。
目次
1章:雇用契約書がないことは違法ではない
先にあげたように、雇用契約書がなくても違法ではありませんが、労働条件が明示されていなければ違法になります。
そのため、会社は雇用契約書に明示すべき労働条件を記載するか、労働条件通知書を交付する必要があります。
そこでこの章では、雇用契約書と労働条件通知書の違いについて説明します。
1-1:雇用契約書とはその内容に合意したことを示す書面
雇用契約書とは、使用者と労働者との間で労働条件や待遇などについて取り決め、お互いにその内容について合意したことを示す書面です。
雇用契約書を交わすことで、労働者は労働条件や待遇について明確に把握することができるため、トラブル防止に役立ちます。
また、雇用契約書は、必ず交付しなければならないというものではありませんが、労働契約法では次のように定められています。
労働契約法第四条:労働契約の内容の理解の促進
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
したがって、労働条件通知書で一方的に労働条件を通知するのではなく、雇用契約書に明示すべき労働条件を記載し、お互いにその内容を確認し締結することが多いです。
労働契約法は、「できるだけこうしてください」というルールですので、違反しても罰則はありません。
そのため、雇用契約書がない場合でも、労働条件通知書が交付されていれば、違法ではありません。
1-2:労働条件通知書とは労働条件を明示した書面
労働条件通知書とは、労働条件を明示した書面で、労働基準法で交付が義務づけられています。
労働者と使用者との間で締結された、「給与」「労働時間」「残業」「休日」などの労働条件について、労働者に明示する書類になります。
このように、雇用契約書と労働条件通知書では、作成する目的が異なります。
雇用契約書は、使用者と労働者の合意内容を明確にする契約書になりますが、労働条件通知書は、使用者が労働者に対して一方的に通知する書類になります。
もし実際に働き出した後で、「労働条件通知書の内容と違った」という場合は、労働者は直ちに雇用契約を打ち切ることができます。
また、雇用契約書は作成する義務はありませんが、労働条件通知書は作成し交付することが義務付けられているため、違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、雇用契約書を兼用し、明示すべき労働条件をすべて記載している場合は、労働条件通知書を作成しなくても違法とはなりません。
実際の一般労働者用の労働条件通知書の見本は、次のようになります。
2章:労働者に明示すべき労働条件
労働者を採用する際には、必ず労働条件を明示しなければなりません。
その中でも、原則書面で明示しなければならない「必ず明示すべきもの」と、退職手当や賞与など「定めをする場合のみ明示すべきもの」があります。
それぞれ解説していきます。
2-1:必ず明示すべきもの(原則書面交付が必要)
原則書面で交付しなければならない、必ず明示すべき労働条件は、次のようになります。
① 労働契約の期間
② 有期労働契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事する業務の内容
④ 始業・終業時刻、休憩、休日などの事項
⑤ 賃金の決定、支払の方法などの事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑦ 昇給に関する事項
① 労働契約の期間
いつからいつまで働く、とあらかじめ決められている契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、その期間が明示されている必要があります。
期間の定めがない契約の場合は、「期間の定めがない」ことが明示されている必要があります。
② 有期労働契約を更新する場合の基準
有期労働契約者の更新の有無や、労働者の勤務成績や会社の経営状況によるなどの、更新の判断基準を明示しなければなりません。
③ 就業の場所、業務の内容
毎日業務を行う場所や、業務の具体的な内容について明示しなければなりません。
④ 始業・終業時刻、休憩、休日などの事項
労働時間については、以下のことが明示されている必要があります。
- 始業・終業時刻
シフト制や日勤、夜勤など日によって就業時間が異なる場合は、勤務パターンごとの始業・終業時間が明示されていなければなりません。 - 残業の有無
- 休憩時間
- 休日の日数
- 休暇の有無
⑤ 賃金の決定、支払の方法などの事項
賃金については、
- 毎月の基本給の金額
- 残業代や休日手当の計算方法、割増率
- 給与の締め日や支払い日
- 控除される項目について
- 支払い方法(手渡しか振り込みか)
などが明示されている必要があります。
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
退職手続きの方法や理由、解雇の理由などを明示する必要があります。
⑦ 昇給に関する事項
昇給の有無や、労働者の実績や会社の経営状況によるなどの、昇給の判断基準を明示しなければなりません。
2-2:定めをする場合のみ明示すべきもの
定めをする場合のみ明示すべき労働条件は、次のようになります。
⑧ 退職手当に関する事項
⑨ 賞与などに関する事項
⑩ 食費や作業用品などの負担に関する事項
⑪ 安全・衛生に関する事項
⑫ 職業訓練に関する事項
⑬ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑭ 表彰、制裁に関する事項
⑮ 休職に関する事項
⑧ 退職手当に関する事項
退職手当が適用される労働者の範囲や、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期になどを明示する必要があります。
⑨ 賞与などに関する事項
賞与や臨時に支払われる賃金などを明示する必要があります。
⑩ 食費や作業用品などの負担に関する事項
労働者に負担させる食費や、作業用品などを明示する必要があります。
⑪ 安全・衛生に関する事項
事業場において必要な安全・衛生に関する事項や、法令に規定されていないが安全衛生上必要なものなどを明示する必要があります。
⑫ 職業訓練に関する事項
会社が定める職業訓練の受講などがある場合には、明示する必要があります。
その他の労働条件も、定めがある場合は明示する必要があります。
雇用契約書がなくても、労働条件通知書が交付されていて、上記のことがしっかり明示されているなら問題ありませんので、一度確認してみてください。
3章:雇用契約書がない場合のありがちなトラブル
ここまで解説したように、雇用契約書は、あなたと会社の間で労働条件や契約内容について確認し、お互いにその内容について合意したことを示す書面です。
しかし、一部の会社では、口頭では良い条件を言いつつ、実際には異なる条件で雇用し、それを説明せずに従業員を働かせることがあります。
こうした会社を避け、トラブルなく働くためにも雇用契約書が必要になります。
雇用契約書がない場合は、以下のようなトラブルや悩みの原因になりかねません。
- 求人票の内容と労働条件が異なる
- 自分に不利な契約や就業規則がある
- 聞いていない試用期間がある
順番に説明します。
3-1:求人票の内容と労働条件が異なる
最も多いのが、入社後になって「求人票に書かれていた条件と違う!」と気付くケースです。
会社によっては、求人票の内容と実際の労働条件が異なることがあるため、求人票の条件を見て入社したのに、実際の労働条件が違っている場合があります。
求人票に書かれた労働条件は、あくまで「目安」です。
そのため、それを悪用して、人を集めるために、わざと、
- 給与を高めに記載する
- 残業を短めに記載する
- 休日を多めに記載する
といった行為をする会社も多いのです。
しかし、労働条件通知書には、実際の条件と異なったことを書くことはできません。
そのため、入社時に労働条件通知書の交付を求め、それをよく読むことでこうしたトラブルを避けることができます。
3-2:会社に有利な契約や就業規則がある
雇用契約書を交付していない会社では、
- 残業をしても残業代を支払わない
- 就業規則に違反したら即時解雇する
など、違法で会社に有利な内容の就業規則を定めている場合があります。
就業規則は会社独自のルールですが、本来なら法律にのっとった内容でなければなりません。
しかし、雇用契約書がない会社の場合、口頭でも労働契約は成立するため、入社後に就業規則をめぐるトラブルが発生するリスクがあります。
3-3:聞いていない試用期間がある
雇用契約書がない場合、会社に入社した最初の数か月を、それまで聞いていない試用期間にされることがあります。
試用期間の場合は、本採用と比べて給与が低かったり、待遇に差が生じるケースが多いです。
本来であれば、会社が試用期間を設ける場合には、雇用契約書や就業規則に明記しておく必要がありますが、雇用契約書もなく口頭での説明も受けていない場合は、後からトラブルになる可能性が高くなります。
4章:雇用契約書・労働条件通知書がない場合の対処法
ここまで説明したように、労働条件通知書がなければ違法ですし、雇用契約書がなければトラブルの元になります。
したがって、労働条件通知書・雇用契約書がない場合は、これから紹介する対処法を実践することが大事です。
- 雇用契約書がない場合の対処法
- 労働条件通知書がない場合の対処法
を順番に解説します。
4-1:雇用契約書がない場合の対処法
雇用契約書がない場合の対処法としては、雇用契約書がないことはそもそも違法ではないため、労働条件通知書の交付を求めましょう。
労働条件通知書がもらえた場合は、その内容をもとに会社に対して労働条件や契約内容について確認し、疑問点がある場合は会社に説明を求めることが重要です。
もし、労働条件通知書の交付を求めても明示されない場合は、雇用期間も定められていないため、2週間前に退職を申し出ることで辞めることができます。
雇用契約書もなく労働条件通知書も交付してもらえない会社は、労働者にとって不利な労働条件を隠している可能性が大きいため、速やかに退職する方が賢明です。
4-2:労働条件通知書がない場合の対処法
労働条件通知書がない場合は、
- 会社に労働条件の明示を求める
- 労働基準監督署に相談する
- 労働問題専門の弁護士に相談する
- 退職する
という対処法を実践してください。
4-2-1:会社に労働条件の明示を求める
労働条件を明示することは、会社の義務です。
そのため、労働条件通知書がもらえていない場合は、まずは会社に対して労働条件の明示を求めましょう
小さな会社の場合は、経営者や担当者が労働条件通知書が必要なことすら知らず、あなたがお願いすることで明示してくれる可能性もあります。
しかし、
「会社に対してそんなこと言えない」
「言っても労働条件を明示してくれない」
という場合は、これから解説する他の方法を実践してください。
4-2-2:労働基準監督署に相談する
労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって全国の会社を監督・指導する行政機関のことです。
全国の都道府県にあり、労働者なら誰でも無料で相談することができます。
労働基準監督署に相談すると、
- 労働基準法にのっとった、具体的なアドバイスをくれる
- 会社に立入調査する
- 会社に対して是正勧告(改善命令)を出す
- 勧告に従わない場合、経営者を逮捕することがある
- 厚生労働省のHPで会社名と違法行為を公開する
などの対応を取ってくれることがあります。
労働条件通知書がないことは違法ですので、会社に対してこうした対応をとり改善してくれる可能性があります。
ただし、労働基準監督署はすべての相談に対して動いてくれるわけではありませんので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【労働基準監督署】相談できることと相談前の準備、相談するメリット
4-2-3:労働問題専門の弁護士に相談する
労働条件通知書がもらえず、それを原因として会社との間で何らかのトラブルが発生している場合、労働問題専門の弁護士に相談することで解決できる可能性があります。
労働問題専門の弁護士に依頼することで、
- 専門知識があるため、迅速に解決できる可能性が高い
- 問題解決に責任を持って取り組んでくれる
などのメリットがあります。
ただし、労働問題弁護士に依頼すると、ある程度の費用が発生しますので、どのくらいの費用が必要か相談時に聞いてみましょう。
労働問題専門の弁護士への依頼方法や選び方について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【保存版】手間、時間、お金をかけずに労働問題を解決するための全知識
4-2-4:退職する
労働条件通知書がない場合、最もトラブルを防げる解決策は「退職する」ことです。
労働条件通知書が交付されない場合は違法であり、労働基準法第15条では、
「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
と定められています。
しかしこの場合、労働条件が明示されていないため、先に解説したように2週間前に退職を申し出ることで辞めることができます。
次の会社に転職するときは、労働条件についてしっかり確認した上で、雇用契約書を交わし入社することをおすすめします。
まとめ:雇用契約書と労働条件
最後に今回の内容をまとめます。
雇用契約書がなくても違法ではないが、労働条件が明示されていなければ違法。
そのため、会社は雇用契約書に明示すべき労働条件を記載するか、労働条件通知書を交付する必要がある。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩、休日などの事項
- 賃金の決定、支払の方法などの事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 昇給に関する事項
- 求人票の内容と労働条件が異なる
- 会社に有利な契約や就業規則がある
- 聞いていない試用期間がある
- 会社に労働条件の明示を求める
- 労働基準監督署に相談する
- 労働問題専門の弁護士に相談する
- 退職する
しっかり雇用契約者や労働条件のルールを覚えて、不利な条件で働かされることがないように気をつけましょう。